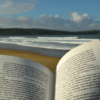FFはどれからプレイすればいい?【この順番がおすすめ】
ドラクエと双璧をなす国民的RPGにして、世界でもっとも人気のあるJRPG、ファイナルファンタジー(FFと略称される)シリーズ。
ナンバリングだけで15作もあります。といっても話のつながりはないタイプなのでどこから入っても大丈夫。
では、どれからプレイすればいいのか?
わたくし1~3と11は未プレイで申し訳ないのですが(1~3はピクセルリマスターが移植されたらやる)、それ以外の作品から入りやすいものを紹介しようと思います。
とはいえこれがけっこうな無理難題。
FFってナンバリングごとに世界観からシステムから一変するんですよね。だからこれだけやっておけばオッケーとはならない。人によって最高傑作候補がぜんぜん違ってきます。
ということで、ここでは次のような段階を踏んでオススメ作品を紹介します。
・今始めるならこれが入りやすいという3作品
・ストーリー重視派向けの名作
・システム重視派向けの名作
・その他の作品も紹介
今からFFを始めるならこの3つがおすすめ
35年の歴史をもつFFシリーズに今から入門。さてどれから手をつければいいのか?
入りやすいのは次の3つです。
・FF7リメイク
・FF16
・FF14
シリーズ代表作 FF7シリーズ(PS4/Switch/PC)
FFの代表作といえばこれ。世界でいちばん人気のあるJRPGです。テレビ朝日で行われたゲーム総選挙では3位、NHKのFF総選挙では2位のゲーム。
なぜこれを最初におすすめするかというと、神ゲーだからというのもありますが、現在進行系でリメイクプロジェクトが展開されているからです。せっかくリアルタイムで楽しめるものがあるなら、それに参加したほうが得ですので。
7は色々とスピンオフとかも出ていますが、次の3つをやっておけば十分。
・FF7原作
・クライシスコアFF7(2022年にリメイクが出た)
・FF7リメイクシリーズ(三部作)
できればこの順番で上からやるのがベスト。ちなみに原作はコマンド戦闘、クライシスコアとリメイクは半アクション戦闘です。
原作は今やっても面白いですよ。とくにストーリーの独創性は異常。たぶん作った本人たちもどうしてこんなものができたのか驚いていると思います。
クライシスコアはFF7の前日談。番外編のなかでは屈指の人気作品。これをやっておかないとリメイクの話についていけなくなるのが厄介なところ。
リメイクは第三部まで終わってみないとどうなるかわかりませんが、第1作目の段階ではけっこう良作でしたし、7のリメイクなら駄作になる可能性は低いと思います。
どうしても昔のグラフィックが嫌で嫌でしょうがないという人だけ、FF7Rから入ればいいと思います。ただしその場合、この作品を100%味わうことはできなくなるのでおすすめはしにくいです。
関連:なぜFF7は神ゲーと評価されるのか【たぶん理由はこの7つ】
激熱アクションRPG FF16(PS5)
2023年に発売されたナンバリング最新作。
作風をひとことで表すと「ダークな少年漫画」です。重く陰鬱な世界観のなかで、常軌を逸した激熱展開が繰り広げられていきます。
熱さと感動の最大瞬間風速ではFF16に敵うゲームはなかなかないと思います。しかも最大瞬間風速がわりとなんども来る。
戦闘が完全なアクションになっている点もポイント。新規からすると逆に入りやすいと思います。最新作という点とあいまって、初心者に本作をおすすめする理由。
シリーズ恒例の要素がふんだんに散りばめられているため、本作をプレイすることでFFのお約束に親しむこともできます。
関連:FF16が期待通りの少年漫画ゲーだった件【評価と感想】
覇権オンラインRPG FF14(PS4/PC)
2013年に発売され、今なお圧倒的な人気を誇っているオンラインRPG。いわゆるMMOと呼ばれるジャンルの頂点です(FFは11と14がオンラインゲーム)。
オンラインに抵抗がないならここから入るのもおすすめ。実際14が初FFという人も多いみたい。
ストーリーの良さでも有名。14は主人公がアバターでプレイヤーの分身なのですが、それを活かした演出が異様に上手い。これほどプレイヤーを号泣させたゲームはなかなかないと思いますよ。
ほとんどのパートをソロで進めることができるのもポイント。ダンジョンのマルチプレイもモンハンの救難信号のようにシステム側が勝手にパーティ構成してくれるので、コミュニケーションの必要がありません。この気軽さもヒットの一因だと思います。
新生→蒼天→紅蓮→漆黒→暁月と続いていきます。今では新生と蒼天が体験版範囲となっており、無料でプレイ可能。
新生こそこれといった長所がなく低評価ですが、蒼天と紅蓮で急に良ゲー化して多くのファンを獲得し、漆黒と暁月では史上最高レベルのストーリーを繰り出して世界中のRPGファンを仰天させました。
関連:FF14がFF10並みに泣ける名作だった件【ストーリー序盤はつまらない】
ストーリー重視派向けの名作はこれ
ストーリーを重視するタイプにおすすめなのは、まだ出てきてないやつから選ぶと次の4作品になるかと思います。
・FF10(特におすすめ)
・FF9
・FF8
・FF6
FFでストーリーの評判がとくにいいのは7,10,14の3作品。この3つは飛び抜けています。
その次に6,8,9,16が来る感じ。とはいえどれが好きかは人による。
ストーリーゲームの最高峰 FF10(PS4/Switch/PC)
異色作にして神ゲーの名をほしいままにする、シリーズ代表作のひとつです。NHKのFF大投票で第1位。テレ朝のゲーム総選挙では第9位。
FFシリーズどころか、あらゆるゲームのなかで最高のシナリオを持つと評価されることもある作品。
また戦闘が従来のATB(時間が流れ続けるコマンド戦闘)ではなく、ゆっくり考えることのできるターン制になっているので、そこも初心者含めた幅広い層におすすめしやすい理由になっています。
よくFFはナンバリングごとにシステムが変わると言われますが、それはだいぶ話を盛っているんですね。しかしFF10は本当にすべてが大きく変わりました。ATBの廃止、スフィア盤によるキャラ育成、マップが一本道、キャラクターボイスの採用、舞台がアジア、主人公が明るいスポーツマン、などなど。
これだけ変えたら普通は駄作になります。クソゲーまっしぐらですよ。しかしそれをシリーズでも上位の神ゲーとして着地させたのが、全盛期スクウェアのスクウェアたるゆえんですね。
スクウェア最後の(12以降はスクエニ)、そしてFF生みの親の坂口博信が関わった最後のオフゲFFがこれです。
絵本のような世界観 FF9(PS4/Switch/PC)
ファンタジックな絵本のような作風が特徴的なFF9。原点回帰を謳ってはいますが、むしろシリーズの異色作といったほうが正しいでしょう。FF界のドラクエって感じ。
世界観のセンスが素晴らしく、もうその時点で勝ち確定みたいな感じ。FFあんまり合わないけど9は好きみたいな人も少なくないと思う。そして女性ファンが多い。
シナリオは坂口博信の思想(生と死)が色濃く反映した、テーマ性の高いものです。エンディングのカタルシスはシリーズでも随一だといえるでしょう。ちなみにED曲はあの白鳥英美子が歌っています。
戦闘周りのテンポが悪いのが作品の足を引っ張る。またジョブシステムのような高度なシステムが搭載されていれば、シリーズ最高傑作の一角になっていたかも。
シリーズ初の学園もの FF8(PS4/Switch/PC)
日本で最高の売り上げを記録したFFがこのFF8です。400万本という恐ろしい数字。社会現象を巻き起こしたドラクエ3が380万本ですから、FF8のすごさがわかります。
マニアックなシステムが特徴。こちらがレベルアップすると敵のレベルも上がったり、魔法を精製して装備品としてセットしたり、なぜか街中の登場人物とカードゲームができたり。
これほど賛否の分かれる作品はFF8とFF12ぐらいかも。FF7やFF10といった大衆的人気を誇る作品のあとに、FF8やFF12といったマニアックな作品を出してしまうところが、よくも悪くもFFという感じ。
注目したいのは音楽の良さ。全盛期FFのトレードマークの一つとして(あるいは最大のトレードマークかもしれない)植松伸夫の音楽があります。彼の才能が絶頂に達したのが、たぶんこのFF8です。FF6までのわかりやすい音楽とは異なるプログレ的な奥深さがあって、作品に強力な陰影を与えています。
シナリオはFF7に勝るとも劣らぬ複雑さで、とてつもない伏線が隠されている系。
2DRPGの完成形 FF6(PS4/スイッチ/PC)
スーファミ最後のFFがこのFF6。
最後の2D作品でもあります。ドットによる表現は極限の領域に達しました。DQ5やクロノトリガーと並び、スーファミのRPGを代表する存在です。
FFってFF5までとFF7以降で作風がだいぶ違います。さてFF6はどっち側なのか?FF5の延長線上にあるともいえるし、FF7はすでにここからスタートしていたともいえる。
実際にはどちらの要素も色濃いです。まさに過渡期の作品であり、見方によっては5までのFFと7以降のFFの良いところをすべてあわせ持った最強の存在と言うこともできるのです。実際、これを最高傑作に推す声も少なくないですね。
味方キャラが10人以上と異様に多く、しかも固定の主人公が存在しません。各キャラにストーリーが用意されていて、いわば全員が主人公。
ストーリー展開も当時としては衝撃的でした。最近でもドラクエ11のストーリーに影響を与えています。
システム重視派向けの名作はこれ
システムを重視するタイプにおすすめなのは次の3作品。
・FF5(特におすすめ)
・FF12
・FFタクティクス
最高傑作候補 FF5(PS4/スイッチ/PC)
ドラクエ5やFF6とともにスーパーファミコンを代表するRPGのひとつ。個人的にはこれかFF7のどちらかがシリーズ最高傑作だと思っています。
なるべく早いうちにこれをやってほしい。なぜかというと、単に神ゲーだからというだけではなく、「ジョブシステム」を採用しているからです。
FFを代表するシステムのひとつがジョブシステム。ナイトとか竜騎士とか忍者とか白魔道士とか黒魔道士とか召喚士とかのあれです。プレイヤーはキャラクターを「ジョブチェンジ」させ、自分なりの育成を楽しむことになります。
そしてこのジョブシステムがもっとも完成度の高い次元で提供されている作品がこのFF5になります。いまだに最高傑作のひとつとされるゆえん。上位互換が存在しないので、この方向性においてはずっと5が王者なわけです。
ジョブシステムを味わわなければFFを味わったことにはならないので、その最高の形であるFF5を最初のうちにプレイすることをおすすめします。
マニア向け神ゲー FF12ゾディアックエイジ(PS4/Switch/PC)
不人気な神ゲーです。
オリジナルはPS2で発売され、のちに様々な改良がほどこされたゾディアックエイジバージョンがPS4やスイッチに移植されました。
音楽とかでもよくありますよね。ものすごく質が高くて評論家や同業者からはいつも高く評価されるのに、売上はいまいちで世間的な知名度はゼロみたいな。そのFF版がこの12。
PS2のゲームとしてはストーリー以外のクオリティが半端じゃないです。やり込みではFF5と双璧をなす面白さか。
また戦闘システムが独創的にすぎることで有名。「ガンビット」を設定してキャラクターに命令を与えます。「味方のHP<50%ならケアルラ」「炎に弱い敵にファイア」「戦闘不能の味方にフェニックスの尾」みたいに。
プログラミングの授業でも始まったのかと思いますよ。合わない人にはとことん合わない(逆もまたしかり)。極めれば極めるほど見てるだけの戦闘になります。とはいえ最適なガンビットを設定し倍速モードで敵をなぎ倒していく爽快感はすごいです。
MMOのシステムをオフゲに落とし込もうとした作品ともいえます。ドラゴンエイジやゼノブレイドの先行者としてもよく名前が挙がりますね。
SRPG版ファイナルファンタジー FFタクティクス(PS/PSP)
FF7とFF8のあいだに発売された外伝作品です。
タクティクスオウガなどの名作SRPGを手掛けた松野泰己による、シミュレーションRPGと化したFF。タクティクスの頭文字を取って、FFTとも呼ばれます。
ジョブシステムを採用している点が特徴。FFの伝統的システムと松野の世界観が融合することによりマジックが生じています。あまりにも神ゲー。
ウィーグラフ戦の前でセーブしてしまい詰みかけたのもいい思い出(あれほど必死に試行錯誤を繰り返したことは人生で他にない気がする)。
SRPGにはファイアーエムブレムなど優れたシリーズが多数存在しますが、100万本を超えるセールスを記録したのはこのFFTだけです。
その他の作品も紹介
ここまで名前が登場しなかった作品をおすすめ順に紹介します。
ATB誕生 FF4(PS4/スイッチ/PC)
ハードがファミコンからスーファミに変わって初めてのFFがこのFF4。ドラマチックなシナリオを採用しキャラを全面に押し出す、いわゆるJRPGの元祖の一つです。
実はシステム面で革新的な作品でもあります。バトルにATB(アクティブ・タイム・バトル)を採用し、コマンド戦闘に時間の概念を導入したのです。
このシステムって今考えてもすごいですよね。コマンドRPGは現在でも色々と出ていますが、結局このFF4より革新的なものはなかったんじゃないでしょうか?
リアルタイムで遊べばとんでもなく革新的なソフトだったのだろうと思われます。しかし現時点で評価するとFF6の下位互換ととれなくもない。ということでこの順位にしました。
隠れた良作 FF零式(PSP/PS4)
PSPで発売された外伝作品。PS4に移植されています。
元々はFF13シリーズ(13、ヴェルサス、アギト)の一環として発表されたものでした。ヴェルサスはFF15になり、アギトはこの零式へと変化します。
正直13シリーズのなかでもっとも優れているのがこれだと思う。
神ゲーとまではいきませんが、ストーリー展開はちゃんとツボを抑え、盛り上がるところで大いに盛り上がります(オープニングムービーの決まり具合は異常)。バンプオブチキンによるエンディング曲もゲーム主題歌としては出色の出来。
仕様キャラクターも十数人と多く、しかもそれぞれにスタイルが違ってアクション戦闘もけっこう面白い(いわばモンハンの武器種ごとにキャラがいる感じ)。
ヴェルサスじゃなくて零式をFF15にしていれば…15はかなりの人気タイトルになったんじゃないでしょうか?
オープンワールド採用 FF15ロイヤルエディション(PS4/PS5/PC)
PS4で発売されたFF15。
オープンワールドを採用している点が特徴です。しかもパーティ制。仲間4人でガヤガヤ移動するオープンワールドゲームは唯一無二。
また戦闘システムはここからシームレスのアクション戦闘に変化しています(これ以降は7リメイクも16もアクション)。
開発の経緯を調べればわかる通り、失敗作なのは間違いないかと思います。開発スタッフが途中で総入れ替えになったり、PVで発表していた場面が製品版では総削除されていたり、ストーリーが歯抜けで後からDLCで補完されたり(なおDLCは途中で打ち切り)、エニックスと合併後のスクウェアが積み重ねてきた悪行のなかでもトップクラスの業として知られます。
しかしつまらないクソゲーかというとそんなことはなく、完全版のロイヤルエディションをプレイすればむしろ良ゲーではあります(その証拠にスチーム版の評価は高い)。
とはいえ元々は13の外伝として作られ、それを強引に「FF15」に変えた異色すぎる作品。これを最初にプレイするとFFについて誤ったイメージが生まれること間違いなし。ということで後ろのほうに回しました。
ATBの極地と女性主人公 FF13(PS3)
PS3で発売されたFF13。初のHDグラフィック作品です。
ストーリー以外は質が高いです(またこのパターン)。ATBの極地としてのコマンド戦闘システム、主人公ライトニングの人気、浜渦正志による幻想的な音楽などなど、いくつもの長所を備えます。
しかし残念なのはストーリー主体の作りなのにそのストーリーが弱い点。
FF12はストーリー以外の遊び要素が強力だから、ストーリーが弱くても作品の力は相当なものがありました。しかしFF13はストーリーに焦点を当てた一本道ゲーム。そこでストーリーを外してしまったため、不評を買ってしまったのです。
なお13は3部作になっていて、13→13-2→ライトニングリターンズというふうに続きます。最後のライトニングリターンズが一番評価高いです(狭き門を通ってライトニングリターンズまで辿り着いた者の数は少ない)。
まとめ
以上のようにFFはナンバリグごとに個性があって、どれが名作なのかについても人によって意見がバラけます。
だから一作だけやって終わりにするのではなく、なるべく色々と手を出してみることをおすすめします。
あえて一般的評価を想定するならだいたいこんな感じになっているかと思います↓
・FF1~6 みんな大好き坂口ファイナルファンタジー
・FF7,10,11,新14 神ゲー最高傑作候補
・FF8,9,12,16 賛否あるけどおおむね高評価
・FF13,15 悪評にまみれし者たち
・旧14 クソゲー
僕がシリーズにスコアつけるならこんな感じになりますかね↓
FF4 80
FF5 95
FF6 80
FF7 95(7Rは85)
FFT 90
FF8 75
FF9 80
FF10 90
FF12 75
FF13 70
FF14 90
FF15 70
FF16 85
ちなみにPSプラスのエクストラに加入すれば7,8,9,10,12,15は無料でプレイできます。PS4かPS5を持っている人はプラスでやるのがおすすめ。
14も新生と蒼天と紅蓮は無料でできます(こっちはプラスに加入する必要もなし)。なお超絶神ゲーになるのは紅蓮の次の漆黒からです。
1~6はピクセルリマスターがスイッチとPS4に移植されたので、このバージョンでプレイすればよいでしょう。特に5がおすすめ。
なおドラクエ版の記事はこちら。