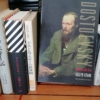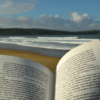『小説家が読むドストエフスキー』小説家兼キリスト教徒ならではの解説
このあいだ読了した『21世紀ドストエフスキーがやってくる』に、亀山郁夫と加賀乙彦の対談が収録されていて、おもしろく読みました。
そのなかで亀山が加賀の『小説家が読むドストエフスキー』(集英社新書)をべた褒めしてたんですよね。
それ以来ずっと気になっていたこの本。先日、中古本屋で見つけ即座に購入。
2003年に朝日カルチャーセンターで行われた講義が元になっています。そのため文章はですます調でなじみやすく、かなり読みやすい。
『死の家の記録』『罪と罰』『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』の5作品が順番に解説されていきます。
カトリック教徒にしてプロの小説家
この『小説家が読むドストエフスキー』には、他書にはない重大な特徴があります。それが以下の2点。
・著者がプロの小説家であること
・著者がキリスト教徒(カトリック)であること
加賀乙彦はプロの小説家にしてキリスト教徒なんですね。なぜこれが重要かというと、ドストエフスキーもプロの小説家にしてキリスト教徒(ロシア正教ですが)だからです。
いわば本書は、同業者が同業者を語るかっこうになるわけです。これは他のドストエフスキー本ではなかなか見られない特徴でしょう。
著者自身この2点を存分に活かして本書を書いています。これが、本書を興味深いものにしている理由です。
プロの小説家だから発見できるドストエフスキーの創作テクニック、キリスト教だから理解できるドストエフスキーの思想。これらへの指摘がふんだんに盛り込まれ、新書ながらも読みごたえのある本になっています。
ドストエフスキーは宗教小説家だ
加賀乙彦の本でとくに重要なのは、ドストエフスキーを宗教小説家と規定している点ですね。
ソ連や日本のドストエフスキー研究には、これは欠けがちな視点なんです。
たとえば小林秀雄のドストエフスキー論は、登場人物の近代的自我うんぬんが問題にされますが、宗教的な次元の話は出てこない。これは間違いであると、加賀ははっきり主張しています。
日本のドストエフスキー研究が平坦なものになりがちなのは、宗教への理解が浅いからというのが大きいと思います。戦前はともかく、戦後の日本人には特にそれが当てはまるでしょう。
ソ連のドストエフスキー研究にも同じことがいえますね。ただしソ連は宗教音痴というよりも、社会主義のドグマが宗教を圧殺していたことの影響です。
社会主義というのは理性と科学を信奉する体制で、宗教はかえりみられませんでした。ドストエフスキーも当時は反動的な作家とカテゴライズされ、あまり人気がなかったらしい。
名高いグロスマンのドストエフスキー伝にしても宗教的な視点はあまり見られず、社会小説としてドストエフスキーを読み解く場合がほとんどです。
ミハイル・バフチンの『ドストエフスキーの詩学』が思想ではなく作品の形式だけに焦点を当てるのも、実は当時の社会体制と関係があります。厳しい検閲体制のもとでドストエフスキーの思想を論じるのはむずかしいですから、そのぶん作品の形式を重点的に語ったというわけです。
今のロシアでドストエフスキー研究がどうなっているのか興味深いですね。
世界の他の地域と同様に、ロシアでも宗教のリバイバルが起こり、ロシア正教の勢いが復活したといいます。それにつれて、ドストエフスキーもナンバーワンの地位に返り咲いたとのこと。
ということは、現在のロシアでは宗教的視点からの深いドストエフスキー研究が行われている可能性が高いですよね。どういう研究がなされているのか、興味深いところです。
印象的だったところ
以下、印象的だった内容をいくつか挙げてみます。
・夏目漱石『吾輩は猫である』の入浴シーンはドストエフスキー『死の家の記録』へのオマージュ。
・シュナイダーの『精神病質人格』はドストエフスキー副読本になる。
・夢や無意識を重視した小説家はドストエフスキーが世界初。
・サルトル以降、人物を外面的に描いてはいけなくなった。
・癲癇の天才はドストエフスキーとナポレオンとマホメット。
・ドストエフスキー作品の登場人物には奥行きがあり、この技術を受け継いだのはプルースト、ジョイス、フォークナー。
・ドストエフスキーは地味な脇役を描くのも上手い。
・白痴は最高傑作である。
・イワンだけ顔の描写がない。
・ドストエフスキーの小説はソナタ形式。
・小説家はストーリーから書き始めては駄目。まずは人物を作り上げること。
・ザビエルの死体は腐らなかった。
・ドストエフスキーはニーチェを読んでいた。
・ドストエフスキーはアンチ社会主義の個人主義者。
本書で加賀は、グロスマンのドストエフスキー伝とベルジャーエフの『ドストエフスキーの世界観』を重要書として挙げています。
両書とも絶版状態で手に入りにくくなっている名著。しかし僕は先日、いずれも古書店で発見しました。しかもどっちも700円。
2冊ともすさまじく面白いので、ドストエフスキーファンの方には中古で探してみることをおすすめします。