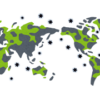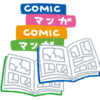なぜ人生は苦しみに満ちているのか?ウォルシュ『神との対話』
ニール・ドナルド・ウォルシュの『神との対話』。
ニールが神と対話した内容を記録したベストセラーです。
1992年、人生に挫折したニールが、神に向かって抗議の文章を書くと、それに対して神から返答がありました。具体的には、ニールの手が勝手に動く自動筆記が始まったのです。
このような現象は、実はそうめずらしくありません。高次元の存在からメッセージを受け取って書かれた名著には、近代以降のものだけでも次のような例があります。
・ステイントン・モーゼス『霊訓』
・オーウェン『ベールの彼方の生活』
・バーバネル『シルバーバーチの霊訓』
・『コース・イン・ミラクル』
・バーバラ・マーシニアック『プレアデスかく語りき』
・ダリル・アンカ『バシャール』
しかし本書が特異なのは、メッセージの送り手が「神」を自称していることです。
霊界の高級霊とか、異星人からのコンタクトではなく、トップオブトップの神からメッセージが送られてきています。
これは本当なのか?僕には判断ができません。
しかし本シリーズを読むと、邪霊のイタズラ的なものであるとは思えなくなってきます。
なぜ人生に苦しみが存在するのか?
ニールは神に対して、「なぜ苦しみは存在するのか」と問いかけます。
すると、神は次のように答えます。
わたしは苦しみを喜ばない。喜ぶという者がいれば、そのひとはわたしを知らないのだ。苦しみは、人間経験に不必要な要素だ。
(ウォルシュ『神との対話』吉田利子訳、以下同書より引用)
ではなぜ苦しみに終止符を打たないのかと問うと、神はこう答えます。
わたしは終止符を打った。わたしが与えた道具を使って苦しみを終わらせるのを、あなたがたが拒んでいるだけだ。
なぜ苦しみを直接消さないのかと問われると、神は答えます。
出来事は、あなたが選択して創り出した時間と空間のなかで起こる──わたしはその選択に決して介入しない。そんなことをしたら、あなたがたを創造した意味がなくなってしまう。
神が世界と人間を創造した理由
ではそもそも、なぜ神は人間を創造したのでしょうか?
それは本書の前半で語られています。きわめて哲学的な議論なので、読解するのはけっこう難しいです。
簡単にいえば、神が自分自身を知るためです。
神が神のまま不動であれば、そこには神というすべてしかなく、神は自分を知ることができません。
そこで、神は自分の外部を生み出し、そこに自分の姿を映し出すことにしたのです。その外部が世界であり人間です。
そして人間には「自由」が与えられました。人生において「しなくてはならない義務はなにもない」。すべてが自由。人間が自由に振る舞えば振る舞うほど、神は自己をより深く知っていくことができます。
ドストエフスキーは「神がいなければすべてが許されしまう」と言いますが、実際には神こそがすべてを許してしまうんですね。
しかしこのへんの議論を見ると、ヘーゲルの哲学はコアの部分は核心をついていたのかもなと思えてきます。
人生の問題の根源:大我 vs 小我
それにしても、神はなんてゲームを始めてしまったんだと思いますよね。

しかし神によると、われわれは自らの意志で人生に参入したのだといいます。しかも多くは死後、みずから進んで人生に戻って来ると。
ここに宗教の、というかこの世界の、厄介さのコアがあります。
あの世にいるわれわれの本体と、この世で劇を演じるこのわれわれとのあいだに、分離があるんですね。東洋の伝統的宗教では前者を「大我」、後者を「小我」と呼んだりします。
厄介なことに、われわれ小我は、大我のくだした意思決定を覚えていないのです。
ネガティブに捉えれば、われわれは大我や神々の使い走りみたいなものですよね。彼らのかわりにダークなゲームに参入して、さんざん苦しんで、山ほどの経験値とともに満身創痍であの世へ帰還するというわけです。
これを受け入れられるかどうか?


伝統的に宗教者が乗り越えようとしてきた問題はこれでした。
「悟りをひらく」とは、自分の正体が小我ではなく大我であるということに、頭ではなく身体で、実感として知るということです。エックハルト・トールの言葉を借りれば、小我とは不幸を生み出す「エゴ」のことですね。
ドストエフスキーもこの境地を目指していました。
彼の理想を託されたのが、ゾシマやアリョーシャといった登場人物です。それに対して、その大我の境地にどうしても納得できず、小我としての自分にこだわるのが、ラスコーリニコフやイワンといった暗い主人公たちなのです。
イワン・カラマーゾフは、神の存在と神が創った世界の存在を認めつつ、それに参入することを拒絶しました。
キルケゴールの言葉を借りれば、大我から切り離された自己は「死に至る病」に侵されています。死に至る病は、絶望。大我の次元を知らない小我は、浅い絶望です。大我の次元を知りつつ、それと和解することを拒む小我は、最大の絶望です。
今度こそ人の不幸は終わるのか?

気が滅入る話になってきたので、ここで別の視点を導入しておきたいと思います。
現代では、数多くの霊的導師たちが「地球が変わろうとしている」と述べます。
きっかけは1987年でした。この年に「ハーモニック・コンバージェンス」と一部から呼ばれる現象が起きます。
簡単にいえば、地球が普通の星になろうと決めたんですね。
地球はいわば地獄星でした。自由と引き換えにありとあらゆる悪徳や苦しみがはびこり、ネガティブな経験データを採取するのにはうってつけの場所。いわば宇宙版のPL学園野球部みたいなものです。
しかし1987年に流れが変わります。地球は地獄星であることをやめると意思決定しました。
結果として、まず、あの世が大掃除されます。われわれが住むこの世の上(ないし横)には「幽界」や「冥界」と呼ばれる次元があり、低級霊や邪悪な霊がウヨウヨしていました。それらの領域が消滅していきます。



そして人間の世界では「風の時代」といったテーマが出てきます。簡単にいえば「苦しみに耐えるのではなくやりたいことをやる時代」みたいなニュアンスです。
これは言い換えれば、もはや苦しみに意味がないということです。
地球は地獄星であり、われわれはそこの現地調査団でした。いわば暗いデータを持ち帰るのが仕事。しかし、地球は「もう地獄星やめよう」と言い出しました。するとわれわれが暗い経験をすることに意味がなくなりますよね。もうそんなこと必要ないわけです。
この無意味さをポジティブに表現すれば、やりたいことをやればいい=風の時代ということになるわけです。
この勢いに乗って、人間の苦しみのゲームも終了に向かう可能性があります。地球に生まれない魂も増えるでしょうし、生まれたとしても、これまでの人類史ような地獄的な人生は減っていくことでしょう。
実際、人類はここ1~2世紀で、かつての人類からは想像もできないほどに民度の高い文明を築き上げつつあります。
現代日本でも、会社や学校や芸能界などいたるところで、昭和的な暗黒ノリが批判にさらされ消えていっていますが、それと似たような事態がもっと大きなスケールでも進行中(昭和以前のノリが消えるのも地球の次元上昇の一環なのかもしれない)。
われわれはすでに一番暗いステージを乗り越えている、あとは良くなっていくだけだ、と考えてもいいのかもしれません。
『神との対話』で印象に残ったところ
・最大の祈りは感謝のことば。逆に、何かを欲するとその対象は手に入らない。何かを欲する自分が手に入るだけ。つまり対象を欲し続ける状態が続く。対象がすでに手元にあると考え、それに感謝するほうが効果がある。
・人生とは、概念として知っていたことを体験的に知る機会。
・人生は学校ではない。新しく学ぶべきことはなにもない。すでに知っていることを思い出すだけ。
・「生きているより死んだほうがいい、という状況はたくさんある」。意識が死を避けていても、魂はすでに死を受け入れている場合が多い。死にゆく者への最大の贈り物は、安らかに死なせてやること。
本巻ではふれられませんが、自殺については大きなデメリットがあるようです。ただし永遠に救われないとかそういうことはなく、超長期的に見ればすべての魂がハッピーエンドを迎えます。「神との対話」シリーズで神は、自殺以外の死を非常にポジティブに語ります。
・真の神とは信者がいちばん多いものではなく、むしろもっとも多くのものに仕える存在。他のすべてのものを神にする存在。
本シリーズを通して、一神教の神ヤハウェは徹底的に批判されます。
・人間関係の目的は、それを通じて「自分がどんな人間であるか」を証明すること。他人ではなく自分を見つめたほうがいい。自分はどんな自分でありたいのか。それを実現する場が人間関係。
・宗教はなんの義務も与えない。むしろすべてを機会として捉えるのが宗教の基盤。すべての問題をチャンスと捉える力が必要。
ニーチェはこの意味での宗教的なレベルに到達したのかも。
・正しいも間違いもない。善も悪もない。ただ、あなたの決断が、あなたが何者なのかを映し出すだけ。価値判断をするとき、人は純粋な創造の場に置かれる。
ハイデガーをこのレベルで理解すべきなのかもしれない。
・人間は身体によって何かを生むために地上にいるのではなく、魂によって何かを生むために地上にいる。
・地獄や最後の審判は存在しない。ただ人間が死後にそれらの経験を作り出すことがあるだけ。
・人間は神の身体であり、神もまたある者の身体である。
ニール・ウォルシュの「神との対話」シリーズのなかでは、死をテーマにした『神へ帰る』が最高傑作と思いました↓
他のスピリチュアル系のおすすめ本はこちらで紹介しています↓