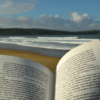退屈との格闘 サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』
20世紀演劇を代表する作品といえば、『ゴドーを待ちながら』。ノーベル文学賞作家サミュエル・ベケットの代表作です。
正直、「批評家が持ち上げているだけの小難しい作品なんだろう」と思っていたのですが、実際に読んでみると、これがおもしろいんです。
一言でいえば、退屈をテーマにした劇作ですね。そこに神学的な暗示が散りばめられることで、作品に形而上学的な奥行きが生まれています。
退屈をテーマにした作品といえば、僕のなかではチェーホフの劇作やブッツァーティの『タタール人の砂漠』がトップでした。ベケットの『ゴドーを待ちながら』は、それらに並んだといってもいい感じです。
『ゴドーを待ちながら』のあらすじ
話の筋はシンプルです。
主人公はエストラゴンとヴラジーミルの二人。退屈のあまり死にそうになっている浮浪者です。彼らが謎の救済者ゴドーをひたすら待ちわびる。
それだけです。
暴君ポッツォと召使いのラッキーが通りかかったり、ゴドーからの伝言を携えた男の子が登場したりしますが、基本的に大きな事件は発生しません。
ゴドーが誰なのかも、ポッツォやラッキー、男の子が誰なのかも明かされません。
ただただ謎めいた語りと暗示が繰り返されるだけ。必死で暇をつぶそうとするエストラゴンとヴラジーミルのふたりの会話を、観客は眺めるだけです。
冒頭の会話を引用してみましょう。
エストラゴン (またあきらめて)どうにもならん。
ヴラジーミル (がに股で、ぎくしゃくと、小刻みな足取りで近づきながら)いや、そうかもしれん。(じっと立ち止まる)そんな考えに取りつかれちゃならんと思ってわたしは、長いこと自分に言い聞かせてきたんだ。ヴラジーミル、まあ考えてみろ、まだなにもかもやってみたわけじゃない。で……また戦い始めた。(戦いのことを思いながら、瞑想にふける。エストラゴンに)やあ、おまえ、またいるな、そこに。
エストラゴン そうかな?
ヴラジーミル うれしいよ、また会えて。もう行っちまったきりだと思ってた。
エストラゴン おれもね。
ヴラジーミル 何をするかな、この再会を祝して……(考える)立ってくれ、ひとつ抱擁しよう。(エストラゴンに手を伸べる)
エストラゴン (いらいらして)あとで、あとで。(サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』安堂信也・高橋康也訳)
こんな会話が200ページくらい、最後までぶっ通しで続きます。
そんな作品のなにがおもしろいのかという感じですが、これがおもしろいんですよね。なぜなのか?
『ゴドーを待ちながら』がおもしろい理由
ベケットの『ゴドーを待ちながら』は何故おもしろいのか。その理由として、まず退屈が見事に表現されている点が挙げられるでしょう。
ショーペンハウアーはかつて「人の一生は苦悩と退屈のあいだを揺れ動く振り子だ」と言い、退屈という状態に苦悩と並ぶ地位を与えました。現代において、この退屈の存在感はいや増すばかりです。
この退屈という魔物、そしてそれと格闘する人間。われわれ現代人のこの死闘が、『ゴドーを待ちながら』には表現されていると思います。
読者や観客はそこに共感を覚え、また慰められるのでしょう。
もう一つの魅力は、神学的な暗示ですね。神学的な暗示が無数に散りばめられることで、作品に奥行きがそなわっています。
同じく退屈を扱った劇作でも、チェーホフには見られない特徴ですね。ある意味ではドストエフスキーに近いか。
劇中の会話はすべてが謎めき、無数の解釈を誘います。
・ゴドーは何者なのか?ゴッド(神)の暗喩なのか?神だとして、その神とは何者なのか?
・ゴドーからの伝言を携えた男の子はだれなのか?預言者なのか?天使なのか?
・ポッツォとラッキーは何者なのか?ひょっとするとポッツォがゴドー(暴君ヤハウェ)なのか?ラッキーがイエスなのか(頭に被せられる花輪)?
・そもそもエストラゴンとヴラジーミルは何者なのか?ほんとうに人間なのか?
このような疑問が読者の頭に到来するかと思います。
『ゴドーを待ちながら』を読み終わると、人はこの作品についてお喋りしたくなると言われているそうです。
それもわかりますが、僕としてはむしろ他の人の解釈を読んでみたいという気持ちが強いですね。説得力のある解釈にであって、スッキリさせてほしいという感じです。