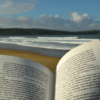洋書でベストセラーを読んでみた【ノンフィクション編】
今までに読んだ洋書のうち、いくつかの感想をまとめておきたいと思います。
この記事はフィクション編に続くノンフィクション編。
フィクション編の記事はこちら↓
- 1. エリン・メイヤー『異文化理解力』 おすすめ度90
- 2. 英語圏のライティングバイブル ジンサー『On Writing Well』 おすすめ度80
- 3. マイケル・サンデル『これからの正義の話をしよう』 おすすめ度80
- 4. マイケル・ルイス『世紀の空売り』 おすすめ度80
- 5. 行動経済学のバイブル カーネマン『ファスト&スロー』 おすすめ度70
- 6. 金融こそが格差を解消する『セイヴィング・キャピタリズム』 おすすめ度80
- 7. 元FRB議長グリーンスパンの自伝『波乱の時代』 おすすめ度70
- 8. アインシュタインの伝記 Walter Isaacson “Einstein His Life And Universe" おすすめ度80
エリン・メイヤー『異文化理解力』 おすすめ度90
文化ごとの慣習の違いを浮き彫りにし、それを理解した上で、異なる文化圏に属する人たちとどう接したらいいのかをアドバイスする本です。文章はものすごく読みやすい。
著者は以下の8つのものさしを使って、それぞれの文化をパターン分けしていきます。
①コミュニケーションがローコンテクストかハイコンテクストか
もっともローコンテクスト(物事を明確に言う)なのはアメリカ、もっともハイコンテクスト(空気を読む)なのは日本。
②マイナスの評価をどう伝えるか
マイナス評価をズバズバ言うのはロシアやドイツ。言わないのは日本などアジア勢。
興味深いことに、アメリカは真ん中。はっきり物事をいうアメリカ人ですが、マイナス評価を口にすることだけは慎重です。
③説得のために原理をもちだすか応用例をもちだすか
原理で説得するのはフランスやイタリア、応用例で説得するのはアメリカ。
アメリカの本がやたら具体例ばかりで読みづらいのはこれが関係しているのかも。
④リーダーシップは民主的か階層的か
リーダーが平等主義なのはオランダなど北欧諸国(バイキングの影響らしい)。
逆に階層的なのは日本や韓国。これは身分の上下を重んじる儒教の影響でしょう。
ここでもアメリカは真ん中。
⑤意思決定は民主的かトップダウンか
民主的に意思決定するのは日本やスウェーデン、トップダウンは中国やインド。アメリカは真ん中。
興味深いのは日本。階層的な身分秩序を重んじるのに、意思決定はトップダウンを避けるのですね。すごく変わってる。これは先の戦争における日本軍研究などでもよく指摘される事実です。
⑥信頼構築はタスクベースか人間関係ベースか
もっともタスクベースなのはアメリカ。基本的に西洋諸国はこっち。
逆に人間関係を重んじるのはサウジアラビアやインド、中国などの非西洋諸国です。もちろん日本もこっち。
⑦対立を避けるか否か
堂々と対立意見を言うのはイスラエル、フランス、ドイツなど。
逆に対立を避けようとするのは日本、タイ、インドネシアなど。日本人が対立を避けようとしがちなのは印象通りですね。
意外なことにアメリカはここでも真ん中。
⑧時間に厳しいかルーズか
時間に厳しいのはドイツ、スイス、日本など。ここに日本が入るのもやっぱりイメージ通り。
ルーズなのはインドやサウジアラビア。フランスが真ん中です。
こういう本を読むと文化的ステレオタイプに囚われてしまうのではないかという意見もありそうですが、著者によると、これはむしろ逆です。
様々なものさしで各文化を相対的に理解することで、慣習のグラデーションや奥行きを見抜く目が養われます。
マクロな視点を抜きにして個人だけを見つめたいという態度を取る人ほど、逆に単純な文化的ステレオタイプに囚われることが多いのです。
本書は文章が読みやすいだけでなく、具体例の挿入も適材適所で好印象。
アメリカの本って冗長なものが多いですよね。ページ数をかさ増しするために、無駄な具体的エピソードを詰め込みまくっています(もしかすると原理ベースではなく応用ベースで説得するアメリカ文化の影響かもしれない)。
しかし本書の具体的な記述は無理がなく、読んでいてストレスがたまりにくいです。
英語圏のライティングバイブル ジンサー『On Writing Well』 おすすめ度80
アメリカでライティングのバイブルとされる本には、双璧をなす2冊があります。一冊はストランク&ホワイトのElements of Style。そしてもう一冊がウィリアム・ジンサーのOn Writing Wellです。
Elements of Styleがマニュアルないし資料のようなテキストなのに対し、こっちは読み物としての性格が強め。わりと楽しく読めます。僕はライティングの勉強のためというより、英語の多読の一環として読みました。ライティングの知識も見について一石二鳥。
引用が多い本です。お手本となる文章をジンサーが引用してきて、それを解説していくスタイル。引用された文章は写経用のテキストとしても使えるかも。
全体は大きく4つのパートに分かれ、全部で24の章があります。4つのパートは以下の通り。
・原則
・方法
・形式
・心構え
原則パートで語られる内容は、たとえば次のようなもの。
・余計な語は削れ
・不特定多数ではなく特定の相手に向けて書け
・ライティング上達は真似をすることから始まる
方法パートで語られる内容は、たとえば次のようなもの。
・序文と末文の書き方
・動詞、形容詞、副詞などの使い方および注意点
・推敲のテクニック
形式パートで語られる内容は、たとえば次のようなもの。
・どの分野について書くのか
・各分野ごとの書き方(スポーツ、旅行、芸術、科学、etc)
・ユーモアの使い方
心構えパートで語られる内容は、たとえば次のようなもの。
・尊敬できる書き手を見つけて徹底的に真似よ
・楽しめる分野で書け
とにかく削れというのは日本の文章術の本でもよく目にする教えです。文章のなかでなんの機能も果たしていない語は、すべて削ってかまわないと。
上手い人の真似をしろという教えもそう。やはり最初は真似から入るのが近道。やがてそこからオリジナルティも出てくるといいます。尊敬する書き手がいる人はラッキーです。
楽しめる分野で書けというのも至言だと思う。とくにライティングの仕事をする人は、これを肝に銘じておいたほうがいいですね。でないとすぐに消耗して、嫌になると思います。
ジンサーの文章はレトリックを多用するタイプで、日本人からするとやや難易度が高いです。案外、洒落た装飾の多い文章な気がする。これを洋書で読もうとするとある程度のリーディング力は求められるかもしれません。
英文ライティングの勉強になるのはもちろんですが、ライティングそのものを洋書で勉強してみたいという人にもオススメできます。日本語で文章を書くときにも応用できる考え方ばかりなので。
マイケル・サンデル『これからの正義の話をしよう』 おすすめ度80
アメリカの哲学者サンデルによる一般向け哲学書。邦題は『これからの正義の話をしよう』で、日本でもベストセラーになりました。
文章は読みやすいです。内容的にはすらすら読める類の本ではありませんが、哲学的な知識がなくても問題なし。
功利主義、リバタリアニズム、カント、ロールズ、アリストテレスなどが取り上げられます。彼らの倫理思想が要約されるだけでなく、現代の様々な現実的問題と彼らの思想を突き合わせることでその思想を批判し、「正義」の輪郭を浮かび上がらせていくというスタイル。
例えばカントの道徳哲学に関する章ではクリントン元大統領の不倫問題が持ちだされ、カントならこれにどうコメントしたかと思考実験することでその思想を吟味したりします。この理論と現実の往復が本書の強み。
マイケル・ルイス『世紀の空売り』 おすすめ度80
マイケル・ルイスによるサブプライムローン関連本。サブプライムローンの詐欺的本性を早くから見抜き、後の危機に乗じて儲けた人たちが主人公です。
サブプライムローン債券は借りてくることができないため空売りもできない、だからCDSをサブプライムローン債券に用いることで実質的な空売りをしたのだという説明は目から鱗。
この人の本は『ライアーズ・ポーカー』も原書で読んだことがあるけれども、かなり難しいです。扱う内容が金融分野だからという面もありますが、文章自体も難解です。
彼の本が売れるのは金融業界に対する批判的な姿勢のためでもありそう。そもそも彼のデビュー作『ライアーズ・ポーカー』は、ソロモンブラザーズを内幕から描くことで金融業界を批判する意図がありました。皮肉なことに、同書はむしろ金融業界を生き抜くための指南書としての評判を得てしまったのでしたが。
行動経済学のバイブル カーネマン『ファスト&スロー』 おすすめ度70
ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマンのベストセラー。経済学の本というより、心理学の本です。ただし心理学といってもフロイトの精神分析学のようなものではなく、良くも悪くも科学的アプローチが主体の現代心理学です。
文章はそこまで難解ではありませんが、読みやすいか読みにくいかといわれたら読みにくいです。ただし専門的な知識がなくても読める本です。この独特な文章は、著者がイスラエル人であることと関係しているかもしれません。
行動経済学は、人がまったく合理的な生き物ではないことを実証します。これは結果的に、従来の経済学が前提としてきた合理的経済人モデルへの批判となります。経済学は合理的な経済人を前提として成り立っているため、行動経済学がその前提を掘り崩すと、大幅な変更を迫られるのです。これが、行動経済学という分野が大きなインパクトをもつ理由です。
それにしても長い本でした。しかも章ごとに毎回クイズをやらされるので、読んでいてくたびれました。要点を上手く整理してくれている本なりサイトなりがあるのなら、そっちを読んで済ませてもいいかもしれません。
金融こそが格差を解消する『セイヴィング・キャピタリズム』 おすすめ度80
金融に良いイメージを持っている人は多くないと思います。なんとなく汚職や経済格差の元凶みたいなイメージがありますよね。
しかし実はその印象は事実と反している。それを実証し声高に主張する本がこのSaving Capitalism from the Capitalist(邦題は『セイヴィング・キャピタリズム』)です。
「資本家から資本主義を救い出せ」というおもしろいタイトル。強力な金融システムこそが格差や汚職を根絶する力なのであり、そのシステムを制限しようとする既得権力をこそ打ち倒せというニュアンスです。富を社会に行き渡らせる金融システムは庶民の味方であり、不平等や格差はむしろ金融システムの本領が発揮されていないことが原因だというわけです。
本書が解き明かすのは次のようなテーマです。
・なぜ自由市場は有益なのか
・自由市場はどのようにして生まれたのか
・なぜ有益なはずの自由市場に反対する勢力がいるのか
・自由市場に反対する勢力は何者なのか
個人が富を得るには、高度な金融システムが不可欠です。しかし十分なインフラを整えるのは簡単ではありません。どうしても政治の力が必要になってくるからです。
しかし少なからぬ政治家にとって自由市場は敵。自分たちの既得権を脅かすからですね。既存の不平等な経済システムから甘い汁を吸っている人びとが、政治家の支持基盤になっていることが多いのです。
したがって経済格差を解消するためには、政治の改革が必要になる。こうして本書のテーマは、市場vs政治というテーマに収斂していきます。
著者らの先輩ミルトン・フリードマンは市場の効率的な作動を前提として政治の介入をしりぞけましたが、シカゴ大学の後輩である著者らによると、その立場は十分なものとはいえないとのこと。市場が効率的であるためには、賢明な政府による制度設計が不可欠なのです。そのコアにあるのが所有権の保護ですね。
考えてみれば、日本は明治政府がなんだかんだで優秀だったおかげで、ここまでの経済大国になったといえます。
弱者を食い物にする悪徳高利貸しがいる。この害悪をどうやったら防げるのか?金融という仕組みそのものを敵視するべきなのでしょうか?
本書はこの問題に対して、「金融システムを強くすることで問題に対処せよ」と教えます。高利貸しが生息できるのは金融システムが不十分なせいであり、強力な金融システムさあれば庶民は低利でお金を借りることができるからですね。
この「金融の害悪を防ぐには高度な金融システムが必要」というロジックは強力です。これは色んなフィールドに応用可能な考え方なのです。たとえば「宗教の害悪を防ぐには高度な宗教が必要なのだ」というふうに。
専門的なテーマを扱っていますが、文章はとても読みやすいです。そもそも英語圏のテキストというのは、小説や新聞よりも専門書の文章のほうが簡単です。
元FRB議長グリーンスパンの自伝『波乱の時代』 おすすめ度70
かつて魔術師と呼ばれ畏怖されていたグリーンスパンですが、近年では2008年の金融危機を生み出した責任を問われることも少なくない模様。『世紀の空売り』の主人公のひとりEismanはグリーンスパンをくそみそに批判していました。
本書はそのグリーンスパンの自伝。当然ながら内容は経済の話がメインになります。ある程度の知識がないと苦労するかも。
政治の話も多いです。なかでもニクソンやフォード、クリントン、ブッシュといった歴代大統領の人物描写が面白い。飛び抜けて頭がよかったのはニクソンとクリントンらしい。ただニクソンは性格面に大きな欠点があったようです。
自伝と銘打っておきながら後半パートは世界経済の分析しかしていないので、そこは注意されたし。
アインシュタインの伝記 Walter Isaacson “Einstein His Life And Universe" おすすめ度80
天才物理学者アインシュタインの伝記。文章は非常に平易で読みやすかったです。数式の類も出てきません。
アインシュタインはまぎれもない天才ですが、意外とそこまでの奇人ではない印象。哲学者のウィトゲンシュタインだとか、音楽家や画家の天才たちに見られるようなエピソードを期待すると、肩透かしを食らうと思います。
アインシュタインは哲学者のヒュームから影響をうけていたらしい。また特に尊敬する科学者はマッハとローレンツ。
一度目の結婚が上手くいかず、精神的ストレスの結果、胃を悪くするに至る。ここらへんのエピソードといい、反抗心のある誇り高き性格といい、どこか夏目漱石を思わせます。
ちなみにシュレーディンガーは物理学における新発見はもうないと諦め哲学に転身しようとしたが、哲学科にポストが得られなかったため物理学にとどまったらしい(波動方程式を生み出すのはその後のこと)。
ハイゼンベルクの不確定性原理は存在論のレベルの話だそう。自然が片方にあって人間がそれを観察するも観察装置の限界や人間の認識能力の限界ゆえに自然の構造が完全には知りえない、と言っているのではなく、そもそも自然には唯一の客観的な構造がないと言っているわけです。
ボーア曰く「物理学とは自然のあり方を究明するものではなく、自然について我々が何を言えるのかを究明するものである」。