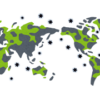学校は必要なのか? イリイチ『脱学校の社会』を解説
学校に通うことが「当たり前」であり、そこから外れることが「問題」とみなされてきた社会は、いま転換点を迎えています。
不登校の増加、学歴の相対化、ITやAIによる学びの脱中心化――それらは偶然の出来事ではなく、社会全体が長く依存してきた「学校化された価値観」が揺らいでいる兆候だといえるでしょう。
イヴァン・イリイチの『脱学校の社会』は、こうした現代の状況を半世紀も前に予見し、学びを制度から解放する可能性を示しました。
以下、わかりやすく解説していきます。
イヴァン・イリイチとは何者か
イヴァン・イリイチ(1926–2002)は、20世紀後半を代表する社会批評家・思想家の一人。
彼は近代社会が当然の前提としてきた「学校」「医療」「交通」「専門家制度」などを根本から問い直し、それらが人間の自立や共同性をむしろ損なっているのではないかと鋭く批判しました。
その思想は教育学、社会学、哲学、政治思想など幅広い分野に影響を与えています。
イリイチはオーストリア・ウィーンに生まれ、ヨーロッパ各地で教育を受けました。神学、哲学、歴史学などを学び、若くしてカトリック司祭となったことも彼の思想形成に大きな影響を与えています。
その後、アメリカやラテンアメリカで活動し、特にメキシコに拠点を置いた「CIDOC(異文化文書センター)」での研究・教育活動を通じて、近代化や開発、教育制度に対する批判を深めていきました。
イリイチの思想の特徴は、制度化された「善」が人間に与える逆説的な害を明らかにしようとした点にあります。
たとえば、教育は本来学びを促進するはずのものですが、学校制度が確立されることで「学ぶこと=学校に通うこと」と同一視され、学校外での学びが過小評価されてしまうと彼は考えました。
同様に、医療は健康を守るための制度であるにもかかわらず、過度に専門家に依存することで人々は自らの身体や生を管理する力を失っていくと指摘しました。
こうした批判の根底にあるのが、イリイチのいう「制度の自己増殖」への警戒です。
制度は一定の規模を超えると、本来の目的から離れ、制度そのものを維持・拡大することを最優先にするようになります。その結果、人間は制度の利用者ではなく、制度に従属する存在へと変えられてしまうのです。
イリイチはこの状態を、人間の自由や自律が奪われた社会の姿として捉えました。ウェーバーのいう「鉄の檻」と同じです。
イリイチは単なる破壊的な批判者ではありませんでした。彼が目指したのは、制度を完全に否定することではなく、人間が自ら学び、助け合い、道具を主体的に使いこなせる社会の回復です。
そのために彼は「コンヴィヴィアル(共に生きる)」という概念を重視し、人間の能力を奪わず、むしろ引き出すような道具や制度のあり方を模索しました。
『脱学校の社会』は、こうしたイリイチの思想が最も鮮明に表れた著作の一つです。この本を理解するためには、彼が近代社会の制度全般に向けていた根源的な問い、すなわち「人間はいつの間に制度のために生きる存在になってしまったのか」という問題意識を押さえておくことが不可欠でしょう。
『脱学校の社会』はどんな本か
『脱学校の社会』は、イヴァン・イリイチが1971年に発表した代表的著作であり、近代社会における学校制度を根本から問い直したラディカルな教育批判の書。
本書は「学校を改善するにはどうすればよいか」ではなく、「そもそも学校という制度は人間の学びにとって必要なのか」という、より根源的な問いを提示しています。
イリイチによれば、近代社会では「学ぶこと」と「学校に通うこと」がほぼ同一視されています。
その結果、人々は学校という制度の外で起こる学び――家庭での経験、仕事を通じた技能習得、友人との対話や読書といった自発的な学習――を正当に評価できなくなっているとされます。
学校は学びを独占する制度となり、「正しい学習とは何か」を一方的に定義する権限を持つようになったのです。
本書で繰り返し強調されるのが、学校制度が生み出す「隠れたカリキュラム」の問題です。
表向きのカリキュラムは知識や技能の習得ですが、実際にはそれ以上に、序列への服従、資格への依存、専門家への信仰といった価値観が無意識のうちに刷り込まれます。
成績や学歴による評価を通じて、人は「学歴がなければ価値が低い」「専門家に任せなければ何もできない」と考えるようになるとイリイチは指摘します。
また、学校制度は平等を掲げながら、実際には不平等を再生産する装置として機能しているとも論じられます。
義務教育が整備され、教育の機会が形式的に平等になったとしても、家庭環境や文化資本の差は学校内で拡大され、学歴という形で固定化されてしまいます。
学校は社会的格差を是正するどころか、正当化してしまうというのがイリイチの厳しい評価です。
こうした批判のうえで、イリイチが提示する代替案が「学習のためのネットワーク(learning webs)」という構想です。
これは学校のような中央集権的な教育機関に依存するのではなく、人々が自らの関心や必要に応じて、知識・技能・人と出会える仕組みを社会全体に張り巡らせるという考え方です。
たとえば、学びたいテーマを公開し合う場、教えられる技能を持つ人と学びたい人を結びつける仕組み、同じ関心を持つ仲間同士が出会うネットワークなどが想定されています。
重要なのは、イリイチが「学校をすべて廃止せよ」と単純に主張しているわけではない点です。
彼の関心は、学びが制度に独占される状態を解体し、人間が本来持っている自発的な学習能力を社会の中で回復することにあります。
『脱学校の社会』とは、学校という建物を壊すことではなく、「学校化された価値観」から私たち自身を解放する試みだといえるでしょう。
今、オンライン学習、オープンエデュケーション、コミュニティベースの学びなどが広がる中で、『脱学校の社会』は再び現実味を帯びています。
学歴や資格に過度に依存する社会のあり方を問い直すうえで、本書は今なお強い示唆を与え続けているのです。
学校化社会の終わり
日本で語られてきた「学校化社会」批判は、イリイチの『脱学校の社会』と親和的です。
学校そのものというよりも、社会全体が学校の論理で動いている状態――年齢主義、序列化、標準化、評価への服従――が問題にされてきました。
日本型の学校化社会の特徴は、学校で身につける価値観が、そのまま企業社会や人生設計にまで延長されている点にあります。
・同年齢集団による一斉進行
・テストや偏差値による序列化
・「脱落者」を想定しない単線的な進路
・努力=我慢=評価されるという道徳
こうした論理は、学校を卒業した後も、学歴主義、年功序列、終身雇用といった形で社会全体に浸透してきました。まさに社会そのものが巨大な学校として機能していたといえます。
しかし、この学校化社会は構造的な限界に直面しているように思われます。
IT化やAI化は、知識や技能を「どこで・誰から・どの順番で学ぶか」という前提を根本から崩しました。知識は学校に独占されるものではなくなり、スキルも資格や学歴を経由せずに可視化・証明できるようになりつつあります。
これは、イリイチが構想した「学習のためのネットワーク」が、技術的に現実化し始めている状況だとも解釈できます。
この文脈で見ると、現在の不登校問題は、個人の適応不全というよりも、システムの側の軋みが表面化した現象と捉える方が妥当でしょう。
学校は依然として、同一の時間割、同一の評価基準、同一の発達モデルを前提に設計されています。しかし子どもたちの認知特性、興味関心、発達速度、家庭環境はますます多様化しています。
その多様性を受け止められないシステムの硬直性が、拒否反応として「不登校」という形で現れていると考えられます。
重要なのは、不登校が「学校に行けない異常な状態」ではなく、学校化社会の前提がもはや自明ではなくなったことを示すシグナルだという点です。
従来の学校は、「そこに通うこと自体が正解である」という規範を前提として成立していました。しかし、その正解が揺らぎ始めたとき、最も感受性の高い層がまず離脱するのは、ある意味で自然なことでもあります。
もっとも、学校化社会が「終わる」といっても、それが一気に崩壊するわけではありません。現実には、学校的価値観と脱学校的な価値観が長く併存する過渡期が続くでしょう。
その過程では、評価や選抜の仕組み、社会保障や労働市場との接続といった難題が避けられません。
それでも確かなのは、学びを学校に閉じ込める社会モデルは、もはや唯一の選択肢ではなくなったということです。
不登校問題は、その転換点を示すもっとも分かりやすい現象の一つであり、イリイチの議論が半世紀を経て再び現実性を帯びている理由も、ここにあるといえるでしょう。
その他、社会学のおすすめ本まとめはこちら↓