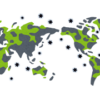あの世を訪問するスウェーデンボルグ『霊界からの手記』【解説】
18世紀を代表する天才科学者にして、人類史上最大の霊能者とも呼ばれるエマヌエル・スウェーデンボルグ。
もともとはヨーロッパを代表する自然科学者として名を馳せていたのですが、中年(56歳)になってから特殊な能力に開眼。肉体を自由に抜け出して霊界を訪れたり、死者とコミュニケーションして紛失物を見つけてあげたり、故郷で起こっている大火災を透視したり、自分がいつ死ぬかを予言し実際その日に寿命がきたりと、超弩級の能力を発揮して当時のヨーロッパを震撼させた人物です。
同時代を生きたドイツの哲学者カントにも多大な影響を与えたことでも知られますね。
彼が「死の技術」によって肉体を抜け出し、精霊界や霊界を訪問したうえでその記録をとどめた本が『天界の秘密』や『霊界日記』といった著作です。そして本書『霊界からの手記』は、それら重要著作からおいしい部分を抽出して日本語訳した作品。
訳文は読みやすいです。ただし霊が語る言葉だけ文語体で訳しているので、そこだけはスラスラとは読めないかも。といっても文語体パートはわずかなものですが。
スウェーデンボルグの存在はカントを通じて以前から知っていましたが、彼の本を読むのは今回が初めてでした。思ってたよりも遥かにすごかったです。正直舐めてました。近代の西洋にこんなとてつもない人物がいたのかという感じ。
もしこれがインド人あたりの著作だったらもっと早くに読んでいたと思う。こういうジャンルに関しては、近代西洋人を侮ってしまう気持ちってないですかね?科学とかは凄いけど、霊学的なことを語らせてもどうせたいしたことないだろう的な。それでスルーしていたんですよね。
本書はそのような油断状態にある読者に、圧倒的な一撃を食らわせます。
霊界からの手記 上巻
本書を読んで思ったのは、確かにどこか科学者的だなということ。
普通こういう本って倫理的なトーンとか美的なトーンが全面に出てきますよね。人はどう生きるべきか、どうしたら心は救われるか、神とは、人生とは、みたいな。
しかしスウェーデンボルグの場合、霊界を含めたこの世界の構造をひたすら客観的に記述している感が強いです。この世界(あの世)はこういうメカニズムになっています的な。
また苛烈な既成宗教(おもにキリスト教)批判も読者を驚かせます。彼は自分の語る事柄が、世間一般の宗教といかに質の違うものであるかをところどころで強調します。
「神」についての話がぜんぜん出てこないのも面白いですね。「天の理」という言葉をスウェーデンボルグはよく使いますが、一神教の人格神みたいな概念は皆無といってもいいのではないでしょうか。
以下、上巻で面白いと思った部分を箇条書きしておきます。
・人間は死後まず精霊界にいく
・精霊界はこの世と霊界のあいだの中間
・精霊界はこの世とそっくり
・霊界には時間と空間の概念が存在しない
・霊界にも文字や数字は存在する
・霊界は3つの層がある
・地獄も悪霊も存在する
・地獄にも3つの層がある
・宗教が説く罰としての地獄落ちはデタラメ
・地獄行きの魂は自らの望みに応じて地獄を選択している
地獄や悪霊が存在するというのはけっこう衝撃的。この手の本ってたいてい「天国しかない」と説かれると思うんです。たとえばニール・ウォルシュの『神との対話』のように。そしてすべてが許されてしまう神の理の異次元さに、人間は戸惑うことになります。だからスウェーデンボルグの説くあの世のほうが合理的ではありますよね。
ただスウェーデンボルグによると、宗教が説くような罰としての地獄落ちはデタラメです。本人の意志に反して落とされるような場所が地獄なのではなく、地獄の悪霊はみずからの自由でそれを選択しているんだと。
釈迦やイエスのいるような天国はどうにも居心地が悪いし退屈だと感じる存在者にとっては、むしろ地獄の利己的世界のほうがよっぽど「天国」なのかも。そう考えると、「天国しかない」という主張と矛盾はしないのかもしれないです。
霊界からの手記 中巻
冒頭でも述べたようにスウェーデンボルグは天才科学者として有名でした。50代半ばに霊能力に目覚めたらしい。かなり遅いですよね。最初は自然発生的にビジョンが見えるようになったこと、次第にそれを意図的に引き起こせるようになったことなどが、中巻の序盤で物語られています。
同時代の哲学者カントについても触れられています。カントはスウェーデンボルグに衝撃を受け、その評伝までも書いていました。
ドイツの哲学者カントも私に会いたいといって人をつかわせてきたことがある。しかし、私は会わなかった。彼も私の能力を不思議な能力と考えたがゆえに私に会いたがった。だが私は、このころには、そんなつまらない平凡な能力のことで、彼ほどの大学者がなぜそれほど大騒ぎをするのだろうと思ったので会わなかったのだ。(『スウェデンボルグの霊界からの手記』今村光一訳)
フォティズムについての記述も興味深いです。なんらかの判断を下したとき、それが正しい結論だったときには赤い暖炉の火が見えるようになったと、スウェーデンボルグは言っています。
思うに、ソクラテスのいう「ダイモーンの合図」ってこれだったのかもしれないですね。ただしソクラテスの場合、ダイモーンの合図があるのは「~するな」という否定形の形を取るのが常だったようですが。
終盤はあの世にいる著名人についての話もあります。
アリストテレスやニュートンが高い霊格をもっていたというのは納得。善人だったかどうかは微妙ですが(とくにニュートン)、二人とも形而上的な関心がベースにあるタイプの思索家ですからね。
逆にパウロを始めとした宗教関係者が低レベルな境遇にいると書かれているのはわりと衝撃。この記述は当時のヨーロッパに大騒動を巻き起こしたそうです。
逆にキリスト教以外の異教徒たちも霊格が高ければ天国にいたとのこと。これも当時のヨーロッパではなかなか見られない発言だったのではないでしょうか。
霊界からの手記 下巻
下巻は自伝的な文章から始まります。父親は宗教的な人間だったこと(スウェーデン語訳の聖書を初めて出版したのも彼)。スウェーデンボルグは自然科学的な関心しかもっておらず、父親から批判されていたこと。40代になって科学的世界観に不十分なものを感じ始め、56歳のとき急に霊的能力に目覚めたこと。
下巻のメインパートは上巻・中巻とはまったく趣が異なり、人類史的な内容になっています。
かつて黄金時代にあった人間たちが、いかに霊的に堕落してきたのか。その原因と過程が解説されていきます。そしてその視点から聖書(とくに創世記)が再解釈されていく。キリスト教への批判は苛烈を極めます。
下巻で面白いと思ったところを箇条書きしておきます。
・霊界にも歴史があること
・古代人は霊的能力をもっていたが時代が下るにつれそれを失った
・アダム(最初に霊性が宿った人間のこと)の時代には地獄はなかった
・アダム以前にも人間は存在した(プリアダマイトと呼ばれる)
・ノアの洪水は第一回目の最後の審判、イエス誕生は第二回目の最後の審判
・イエスは悪霊を地獄に閉じ込めてその影響が霊界や人間界に及ばないようにした
・パウロ同様、ルターは地獄にいた
・ルターの誤りは信仰と行為を切り離して前者のみで十分と主張したこと
・悪霊を遠ざけるには意志の力が必要だが信仰のみでは意志は本物の力になれない
上述したように実践的なトーンの薄い本書ですが、例外は信仰と行為の一致を説くところですかね。信仰だけじゃ駄目なんだと。それが善行として形にされなければ意味がないんだと、スウェーデンボルグは何度も繰り返し強調します。
黄金時代には認識と意志は一致していたらしい。それが次第に分離し、ルターの宗教改革にいたって「信仰さえあれば天国に行ける」と説かれ始めた。スウェーデンボルグはこれを痛烈に批判しているわけですね。
信仰だけじゃ意味がない。意志がなければ悪霊には太刀打ちできない。そして意志が本当の力になるのは行為としてそれが実行されたときだと説かれます。
スウェーデンボルグは何を見たのか?
ニール・ウォルシュの『神へ帰る』によると、人間は死後の第2段階で、生前に信じていた死後の世界を創造するそうです。
関連:神が解説する死後の世界 ニール・ウォルシュ『神へ帰る』【書評】
天国があると思っていれば思っていた通りの天国が創造され、地獄があると思っていれば思っていた通りの地獄が創造される。
これが本当だとすると、スウェーデンボルグが目撃したものの解釈も違ってくるように思う。
スウェーデンボルグは実体として存在する天国や地獄を訪問したのではなくて、死者たちが死後の第2段階において想像&創造している死後の世界を共有したのではないでしょうか?
個人的にはこれがもっとも可能性の高い線かなと思います。