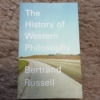初期ドストエフスキーの重要作品『二重人格』【隠れた良作】
『貧しき人々』で鮮烈なデビューを果たし、文壇の寵児となったドストエフスキー。彼が自信満々で世に送り出した2作目が『二重人格』です。
岩波文庫版で十数年ぶりに再読してみました。これが2周目です。
主人公ゴリャートキンは平凡な官吏。当時のロシア文学に典型的な中年男性です。鉄の檻のような近代社会。そこに取り込まれて身動きできない卑小な自分。しかし自尊心だけは膨れあがっていく…
ゴリャートキンは被害妄想に取り憑かれ、しまいにはその妄想からもう一つの人格が生成、ゴリャートキンのドッペルゲンガーを出現させるに至ります。そしてこの新ゴリャートキンが抜け目なく立ち回り、旧ゴリャートキンを追い詰め、その地位を掘り崩していく…という流れ。
暗示、暗示で物語られる作風はすでにここで確立されています。話がすごくわかりづらい。分身が本当に存在するのか、ゴリャートキンにしか見えていない幻覚なのか、それもいまいちわからない(解説などを読むとゴリャートキンの幻覚らしい)。
ゴーゴリやレールモントフの影響も強く、ドストエフスキー史上もっともゴーゴリの影響が強い作品と言われています(とくに『鼻』)。
個人的には序盤がおもしろいと感じました。
とくに主人公がパーティで醜態を演じる場面は名シーン(このへんのゴリャートキンに共感を覚えない読者は幸福な人間です)。その帰り道、恥ずかしさのあまり内面的に破滅しかけているゴリャートキンの前に、ついに彼の分身が現れます。
だが突然…突然彼は全身をぎくりと震わせると、思わず二歩ばかりわきのほうへ飛びのいた。言いようのない不安にかられて、彼はぐるりとあたりを見まわしはじめた。だが誰もいない、なにも変わったことは起こっていなかった。――だがそれにもかかわらず…それにもかかわらず、誰かがいま、たったいま、彼のかたわらに、彼と並んで、同じように河岸の欄干にもたれていたように、彼には思われたのである。(ドストエフスキー『二重人格』小沼文彦訳)
ここが本作のピークではないかと。このへんは後の名作にも劣らないパワーをもっている気がします。
発売当時の評判は賛否両論で、次第に否に傾いていき、ついにはほとんど忘れ去られたこの作品。しかしドストエフスキーはこの作品を終生大切に思っていたそう。実際、「私は後にも先にもこのイデー以上に重大なものは暑かったことがない」と後年の『作家の日記』のなかでも述べています。
その重大なイデーとはなんでしょうか?
自己の分裂がそれです。このモチーフは捨て去られることなく、むしろ後年の作品でさらに深く追求されていきます。
たとえば『カラマーゾフの兄弟』におけるイワン。スメルジャコフと悪魔は彼の分身であり、いずれもイワンとの内的対話を繰り広げます。
そういえば『二重人格』において、下男のペトルーシカがゴリャートキンの窮地を見抜き態度を豹変させるシーンは、イワンとスメルジャコフの関係変化を思わせますね(それぞれの役回りや内面的深さはまったく違いますが)。
他にも『罪と罰』のスヴィドリガイロフはラスコーリニコフの分身ですし、『悪霊』のスタヴローギンはいくつもの分身に分裂しています。
『二重人格』というと突飛な展開をする地味な作品みたいなイメージがありますが、実は後年の名作につながるメインテーマが初めてここで打ち出されているわけですね。
優先的に読むべき作品ではないですが、ドストエフスキーファンなら一読しておいても損はないと思います。
関連:ドストエフスキーの小説はどれから読むべきか?【この順番がおすすめ】
さて次は同じくドストエフスキーの『虐げられた人々』(新潮文庫)を再読していこうと思います。