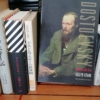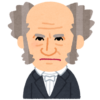実存主義の震源地 ドストエフスキー『地下室の手記』
ドストエフスキーの『地下室の手記』を再読。
今回で3回目。最初に光文社バージョンで読み、次に新潮文庫の江川訳、それから今回また光文社の新訳で読み直したかたち。
この本に関しては、光文社古典新訳文庫の訳のほうが新潮文庫よりもいいと思います。原作の荒々しいパワーがうまく表現されている感じ。
一人称も江川訳が「ぼく」なのに対して、こちらは「俺」で統一されています。このほうが合ってる気がする。
『地下室の手記』はどんな作品か?
ドストエフスキーの『地下室の手記』は、1864年に発表された中編小説。彼の創作活動における転機をなす重要作品です。
物語は「地下室の人」と呼ばれる匿名の語り手(40代のおじさん)の独白によって構成されており、彼の精神的苦悩と社会に対する反抗心が、全編を通して赤裸々に描かれていきます。
この語り手は、かつて官吏として働いていたものの、社会との関係を絶ち、ペテルブルクの地下のような安アパートでひっそりと暮らしています。いわゆる引きこもり的な存在です。
彼は極度に自己意識が強く、理性を絶対視する当時の合理主義的な思想や、啓蒙思想の「人間は理性によって幸福になれる」とする楽観主義に激しい反発を示します。
人間は決して計算通りに行動する機械ではなく、時には自分の不幸を知りながらあえて不合理な選択をする存在である、というのがこの作品の中心的なトーン。
特に有名なのは、「2たす2が4になることさえも、時には腹立たしい」という発言に象徴されるように、論理や科学で説明できない「人間の自由意志」へのこだわりです。たとえその自由が自己破壊的であっても、それこそが人間らしさの証だと語り手は信じています。
このようなテーマは、のちの実存主義、特にサルトルやカミュといった20世紀の思想家に大きな影響を与えました。本書が実存主義の先駆けとも言われる理由です。
物語の後半では、地下室の男が実際に社会との接触を試み、ある女性との出会いを通して一時的に心を開こうとしかけるエピソードが語られます。最終的には彼自身の屈折した性格と深い自己否定によってその関係は壊れてしまい、救いのない終幕へと向かいます。
今日、このような地下室人はもはやめずらしくもなんともない存在ですよね。ドストエフスキーの先進性、現代における彼の重要性が、本書を読んでもよくわかると思います。
この本の主人公(地下室住人)に自分自身と似ている面を見いださない人は幸せです。残念なことに、僕は主人公に共感できるところがけっこうあります。
第一部と第二部のつながりはどうなってる?
『地下室の手記』は第1部と第2部がわかれているのですが、そのつながりを理解するのがむずかしい気がします。ここの連関がどうなっているのか、正直よくわからない。
まずはジョセフ・フランクのドストエフスキー伝を手がかりにして、それぞれの部を簡単に整理してみましょう。
第1部は合理主義への批判
第1部は現在の主人公の語りです。合理主義への批判がその基本トーン。
標的にされるのはチェルヌシェフスキーが書いた『何をなすべきか』という当時のベストセラー小説。これは「理性的エゴイズム」を標榜しており、各人が自分の欲望を合理的に追求すれば世界は良くなっていくという楽観的な思想が特徴です。
東浩紀が『観光客の哲学』で指摘したように、チェルヌシェフスキーのこの思想は現代のグローバリストたちに通じるものがあります。きわめて「進歩的」な考えなわけです。
そして『地下室の手記』の主人公は、その思想を批判しまくります。
主人公が述べるマゾヒズム的な志向も、その文脈で読まなくてはなりません。単におかしな性癖を自慢しているとかではなく、「人間はこんなにわけのわからないことをしでかしてしまえるんだぞ」と合理主義者たちに見せつけて、彼らの哲学を反駁しようとしているわけです。
難しいのは、この地下室住人の主張がどこまでドストエフスキー本人の考えと一致しているかということ。たぶんほとんど一致しているんじゃないかとは思うんですが、どうでしょうかね。
過去の自分たちを批判する第2部
『地下室の手記』はここからひねりが加えられて、第2部では過去の主人公のエピソードが語られます。1840年代の主人公のエピソードです。
1840年代のロシア人エリートの批判がその主題。過去のドストエフスキー自身もそのなかに入っています。
1840年代は空想的な理想主義がロシア人エリートのあいだで蔓延していました。西洋から入ってきた進歩的な思想を受け売りし、それを吹聴するような。読書に耽溺し、現実の社会から遊離してしまっているところがポイントになります。
第2部の主人公は1840年代のエリートを戯画化したものにほかなりません。その主人公の破滅を描くことで、過去の自分たちを批判しているわけです。
リーザという女性が自閉的なエゴイズム打ち破る原理をもたらすのですが、主人公はそれに応えることができず、地下室へと滑り落ちていきます。
その行き着く先が第1部の主人公というわけです。
第1部と第2部の関係はどうなっている?
ここでよくわからないのが、第1部と第2部の関係。
第2部では過去の地下室住人が批判されたのでした。そしてその行き着く先の未来(第1部)で、地下室住人はチェルヌシェフスキーの合理主義を批判している。
批判されるべきものがチェルヌシェフスキーを批判するという、なんだか難しい構造になっているわけです。
ひょっとすると地下室住人も成長しているのかもしれません。第2部の主人公が1840年代のドストエフスキー本人だったように、第1部の主人公は現在のドストエフスキーなのかもしれない。
『地下室の手記』はドストエフスキー文学の転回地点となった重要な作品であり、その威力は現代においてむしろいや増していると思います。今や世界中、地下室住人だらけですからね。
ジョセフ・フランクが指摘するように、本作をドストエフスキーが意図した文脈から抜き出して理解するとその真の意味を理解できなくなってしまうとは思います。
とはいえ、作品自体のもつ異常なパワーは19世紀ロシアでなくても発現します。
ドストエフスキーのおすすめ作品は、以下の記事でまとめて紹介しています↓