ライプニッツのモナドロジー、岩波文庫か中公クラシックスどっちで読む?
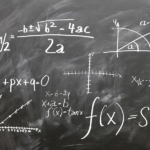
千年にひとりの天才ともいわれるライプニッツ(たしか坂部恵の発言)。微分積分を発明した数学者としても有名です。
そしてライプニッツの哲学的アイデアを封じ込めた断片が『モナドロジー』と呼ばれる作品。
リンク2019 ...
ハイデガー退屈論の再解釈 國分功一郎『暇と退屈の倫理学』

國分功一郎のベストセラー『暇と退屈の倫理学』。
人間は暇や退屈とどう向き合って生きるべきなのか?
これが本書のテーマです。
本書は「倫理学」ですから「~すべき」という主張が出てきます。これがたとえば「退屈 ...