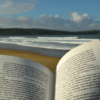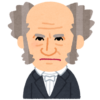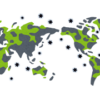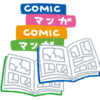西洋中世哲学に楽しく入門できる貴重な本『中世の覚醒』
西ヨーロッパ史上最大の知的革命はなにか?
ニュートン物理学か、それともダーウィンの進化論か。
いやむしろアリストテレスの再発見がそれだ。こう述べるのは『中世の覚醒 アリストテレス再発見から知の革命へ』(ちくま学芸文庫)の著者、リチャード・ルーベンスタインです。
アリストテレスの再発見がいかに西ヨーロッパを激震させたか。この問題を中心に置きつつ、本書『中世の覚醒』は西ヨーロッパの中世思想史を物語ります。
著者は政治学畑の人。中世哲学の専門家ではないので、それが功を奏し、キャッチーで読みやすい思想史の本になっています。この分野ではきわめて珍しい存在。
中世哲学に関心のある人はこれから入るのがいいと思いますね。
アリストテレスの伝記からローマ帝国の終焉まで
本書は中世がメインテーマですが、アリストテレスやその直後の古代世界についても書かれている点も魅力です。個人的にはここがいちばん面白かった印象。
アリストテレスについては、幼少時代から死までかなりくわしく解説されます。たとえば…
・アリストテレスは医者の息子だった
・それがプラトンらの数学的な世界観とは別の方向にアリストテレスを導いた
・マケドニア王家と親密な関係にあった
・アレクサンドロス大王の家庭教師を務めたこと
などなど。
アリストテレスがアテネよりむしろマケドニアと親密な関係にあったことは、改めて強調されるとけっこうインパクトあります。たとえばアリストテレスの学園リュケイオンの保護者が、マケドニアのアテネ総督アンティパトロス将軍だったことなど。
アレクサンドロス大王が遠征先で倒れると、アテネ市民はマケドニアに反旗を翻し、アリストテレスに対しても涜神罪で起訴しようとします。
これを受けてアリストテレスはカルキスに亡命、寂しく生涯を終えることになりました。
アウグスティヌスからボエティウスまで
アリストテレスに続いて、プラトンとプロティノスを応用してキリスト教神学を打ち立てたアウグスティヌスや、「最後のローマの哲学者にして最初のスコラ学者」ボエティウス、彼らの伝記も登場します。
とくにボエティウスについて書かれたものは貴重だと思う。
彼はアテネのアカデメイアで学んだ最後の世代だったんですね。プラトンとアリストテレスの哲学を、キリスト教神学の問題を解くために応用していました。
ボエティウスはやがて東ゴート族の王テオドリックに見いだされ、東ゴート王国の宰相を務めます。
ボエティウスがラテン語に翻訳したギシリアの著作は、その後500年間、来たるべき時を修道院のなかで待ちわびます。
先進文明イスラムから流入したアリストテレス
アリストテレスの著作は、ギリシアローマから直接ヨーロッパに継承されたのではありませんでした。
むしろイスラム世界こそがギリシアの遺産を引き継ぎ、発展させていたのでした(当時の文明の中心はアラビア世界で、ヨーロッパは片田舎)。
しかし12世紀になると、スペインを経由してキリスト教世界にアリストテレスが流入してきます。これが中世ヨーロッパ人に与えた衝撃は空前絶後のものでした。ルーベンスタインは次のように言います。
中世のキリスト教徒が初めてアリストテレスの著作を読んだときのことをたとえていうなら、現代人が古代のパピルス文書を読んで、恒星間空間の移動法やエイズの治療法が書いてあるのを発見するようなものだった。
(ルーベンスタイン『中世の覚醒』小沢千重子訳)
こうしてヨーロッパ人は、イスラム文明から様々な知見を得ることになります。
イスラム世界に足を踏み入れた当時のヨーロッパ人は、ちょうど近代欧米を見学した明治の日本人みたいな感じだったと思います。
ヨーロッパはどのようにアリストテレスを迎え入れたか
さてキリスト教世界はどのようにアリストテレスと対峙したのでしょうか。3つの立場がありました。
・保守的アウグスティヌス主義
・ラテン・アヴェロエス主義
・中道的アリストテレス主義
保守的アウグスティヌス主義は、従来の伝統にべったりと従い、アリストテレスを無視する立場。
ラテン・アヴェロエス主義は、逆に新時代の知識をすべて受け入れる立場です。とはいえ、古い教会の教えは別枠として温存しますが。
そして中道的アリストテレス主義は、キリスト教とアリストテレスを対話させることで新次元の神学を生み出そうとするもっとも革新的な立場です。これの代表者があのトマス・アクィナスです。
本書ではアベラール、シゲルス、アクィナス、スコトゥス、オッカムらが伝記的エピソードを中心に解説されていきます。世界史の復習にもなりそうな内容。
正直なところ、ルーベンスタインの筆をもってしても中世の話はわりと退屈です。このへんを面白く読める人は才能あると思います。
ついでにいっておくと、トマス・アクィナスについては山本芳久の『トマス・アクィナス 理性と神秘』(岩波新書)もわかりやすいです。山本は『中世の覚醒』巻末の解説も書いています。
イスラムとユダヤについての記述は少なめ
中世において西洋は周辺的な片田舎で、イスラム世界が文明や学問の中心地でした。
しかし本書では、イスラム世界の哲学者についてはほんの少しふれるだけにとどまっています。
とはいえ興味深い話もあって、たとえばイスラムの天才哲学者たちは市井の人間だったらしい。したがってイスラム教のメインストリームに対する影響力は限定的だったんですね。
それに対して西洋の哲学者はキリスト教会のインサイダーでした。そして当時のカトリック教会は西洋社会を統合する圧倒的な力をもっていた。ということは、西洋の哲学者たちの思考に革命が生じると、それが社会全体を変えることになります。
ここがイスラムとキリスト教世界の違いにつながったと著者は見ているようです。
解説で山本芳久が述べているように、イスラム哲学に関心のある人には井筒俊彦の『イスラーム思想史』がおすすめ。井筒は世界にその名が知られる天才です。
さらに山本は中世哲学のおすすめ書としてユリウス・グットマンの『ユダヤ哲学』を挙げています。
これ僕は未読ですが、いつか読んでみたい気持ち。
ザラデルがユダヤ思想とハイデガーの類似性を指摘しているのを読んで以来、ユダヤ思想に興味あるんですよね。
その他、哲学史のおすすめ本については以下の記事を参考のこと。