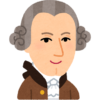ニーチェ哲学をわかりやすく解説【超人から永遠回帰まで】
ニーチェほど体系的な解説を拒む思想家もめずらしいですよね。
ニーチェの著作は短い断章を書き連ねるアフォリズム形式を採用することで有名です。ある時はこう言ったかと思うと、またある時にはそれと矛盾したことを言い出す。
したがってニーチェの文章をひとつの観点から整理し、「ニーチェはこんなことを言いました」と要約するのはきわめて難しいのです。
僕が知る限り、それに成功しているように見えるほとんど唯一の例外が清水真木の『ニーチェ』です。
元は講談社選書メチエから発売されていた本。いまではちくま学芸文庫で入手できます。久々に読み返したらやっぱり明快だったので、僕なりに整理しておこうと思います。
本書の特徴は「病気と健康」の観点からニーチェ哲学を読み解いていくところにあります。
これが著者の勝手な視点設定かというとそうでもありません。ニーチェ本人が自身の作品に後から書き足した序文でそういう趣旨のことを言っているんですね。またルー・ザロメのニーチェ論に同様の視点が見られ、それをニーチェ本人が肯定しているところも根拠です(ニーチェがルー・ザロメに寄せた説もある)。
こうして本書はニーチェの指示に従い、「病気と健康」を導きの糸として彼の作品や諸概念を読み解いていきます。
ニーチェは病人だった
ニーチェは重度の病人でした。後年の発狂が有名ですが、実は若い頃から病気に悩まされっぱなしの生活を送っていたのです。20代前半で大学教授になる天才でしたが、病気を理由に退職。その後は年金をもらいながら、療養もかねてヨーロッパを彷徨します。
そんなニーチェですから、自身の哲学でも健康と病気がキーワードになります。身体に健康と病気があるように、認識にも健康と病気がある。
こうして病気とその反対概念である健康こそがニーチェ思想のコアになります。
では健康な認識、病的な認識とはなんでしょうか?
これは健康な身体から考えてみるとわかりやすいです。健康な身体というのはいわば大きな負荷に耐えられる強靭な肉体ですよね。逆に健康でない身体とは、負荷に耐えられず安楽を必要とする肉体のことをいいます。
ニーチェいわく健康な精神にもこれと同じことが当てはまります。つまり大きな負荷に耐えられるのが健康な精神であり、逆に負荷を避けてなるべく安楽を求めようとする精神は病んだ精神だというわけです。
ニーチェの思想とは要するに、病んだ精神の記録とそれへの批判であり、また健康な精神を追い求める挑戦にほかなりません。
超人、永劫回帰の意味するところ
精神が健康であればあるほど、大きな負荷を人は求めるとニーチェは判断します。思えばデビュー作『悲劇の誕生』の時点でこのような視点はありますよね。
彼が古代ギリシアを持ち上げるのは、大きな負荷(ギリシア悲劇)をあえて自らに課しそれに耐えられるほどの健康さを誇った文化を評価したからでした。そして、そのような負荷を取り除き合理性だけですべてを覆わんとした革命児ソクラテスが断罪されるのがあの作品です。ニーチェの視点からするとソクラテスは病んでいるわけですね。
キリスト教批判なんかも同様の観点から整理できます。絶対的な真理を探すのは安逸を求める病んだ精神。科学だろうと宗教だろうとそれは同じ(消極的ニヒリズム)。絶対的な真理なんて存在しない、この負荷に耐えられるのが健康な精神だというわけです(積極的ニヒリズム)。
ニーチェ本人の概念もこの観点から理解できます。たとえば超人。負荷をどんどん大きくしていって、考えられる限り最大の負荷を精神にかける。この最大の負荷に耐えられるほど健康な人間、それが超人と呼ばれます。
では最大の負荷とは何でしょうか?
それが永劫回帰のアイデアです。この一生が永遠に繰り返す。ニーチェにとってこれは耐えるのが不可能なほどに大きな負荷を意味しました。
この極限の負荷に耐えられる健康体、それが超人というわけです。永劫回帰とは、人が超人であるか否かを測るための試金石、作業仮説にすぎません(宇宙の存在構造とかを述べているわけではない)。
こうしてみると永劫回帰を最大の負荷と考えるところにニーチェの特徴が見て取れますね。たぶん人によっては、たとえば死とか自我の消滅のほうが負荷を感じると思います。永遠にこの人生が繰り返すならむしろラッキーと感じるような人。逆にニーチェは、死というものに恐怖を感じないタイプだったんでしょうね。この人生が何回も繰り返すほうがよっぽど嫌だわと感じるタイプ。だから永劫回帰が最大の重しになるわけです。
読む価値があるのはジンメルとハイデガーとハーバーマスのニーチェ論
本書の後書きで清水も認めているように、ニーチェ解釈に定説はありません。とはいえ強大な影響力をもつニーチェ解釈というものは存在します。著者によると、読む価値があるのはジンメルとハイデガーとハーバーマスの3人だそうです。
僕はハイデガーのニーチェ講義だけ読んだことがあります。これは平凡社ライブラリーで入手できます。ハイデガーは清水とは真逆に、深淵で壮大な哲学体系をもった形而上学者としてニーチェを描き出します(そしてそれを自分で倒す)。権力への意志が本質存在に、永劫回帰が事実存在に対応し、この枠組を使って存在をとらえるニーチェは西洋形而上学の終着点である、というのがハイデガーの理解。
ジンメルのは『ショーペンハウアーとニーチェ』、ハーバーマスのは『近代の哲学的ディスクルス』という本。僕はどっちも読んだことありませんが、ジンメルのはいつか読みたい。
個人的にはシュタイナー『ニーチェ 自らの時代と闘うもの』もおすすめ。
清水真木はニーチェには深遠さがないと評価しています。これは自分も同意見。僕はグル(導師)とかが書いた宗教系の本もよく読むんですが、ニーチェの著作ってそのような深みとか波動がほとんど感じられないんですよね。深遠さがない点をプラスに評価したい人もいるとは思いますが、僕はここにニーチェの限界があると思います。近代という一時代の常識に絡め取られてしまっている部分が、見た目に反して実はあります。
シュタイナーの本、とくに後半の講演録は、このような観点からニーチェの真価と限界を評価していて参考になります。