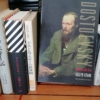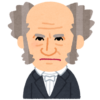ドストエフスキーの『未成年』は何故つまらないのか
ドストエフスキーの長編で、もっとも人気のない作品はどれでしょうか?
答えは『未成年』です。
後期の5大小説の一角をなしながらも、ほとんど語られることのないこの作品。
『カラーマゾフの兄弟』は世界文学の最高峰として、『罪と罰』は一般人気で、『悪霊』は知識人への影響力で、『白痴』は女性ファンの多さで、それぞれ不動の地位をほしいままにしています。
が、『未成年』にはこれといった特徴もない。
『未成年』に特徴があるとしたら、「あのドストエフスキーの小説なのにあんまり面白くない」という点でしょうか。
『未成年』を一番好きという人は見たことがないですよ。
『未成年』を読み返してみた
今回ドストエフスキー作品を再読する一環として、『未成年』(新潮文庫版)も読みました。
読むのはこれが2回目。全開読んだのはたしか2012年でしょうか。7年ぶりということになります。内容はまったく覚えていませんでした。
読んだ感想としては、やっぱり面白くないですね←
全盛期ドストエフスキーが、あの『悪霊』と『カラマーゾフの兄弟』のあいだに書いた小説なのに面白くない。これは本当に不思議なことです。
そしてめちゃくちゃ難しい。
この難解さは異常。おそらくドストエフスキー作品のなかでもっとも難解な小説がこの『未成年』です。
なぜ『未成年』は面白くないのか、そして難解なのか?
主人公の一人称視点とポリフォニーは相性が悪い
この『未成年』という小説は、ドストエフスキーにはめずらしく主人公の一人称で物語が展開します。
おそらくここに、つまらなさと難解さの秘密があります。
ミハイル・バフチンが指摘したように、ドストエフスキー小説の最大の特徴はそのポリフォニー性(多声性)にあります。俗っぽい言い方をすれば、キャラ立ちが異常なレベルで成立しているということ。
主人公だけでなくすべての登場人物がそれぞれの世界を持ち、作家の手からすらも独立して躍動する。これがドストエフスキーの神業です。
しかし主人公の一人称だと、このポリフォニー性が発揮されにくいと思うんですね。キャラが立ち上がってこない。主人公の声ばかりが聞こえてくるわけですから。
ドストエフスキーの小説は、一人称と相性が悪いといえます。
『未成年』が面白くない理由の一つは、おそらくこれでしょう。
読みにくさも一人称が原因
また異常な難解さも主人公の一人称と関係があります。
一人称のナレーションですから、読者は主人公の視野で作品世界を眺めるわけですよね。
本作の場合、その主人公の視界が歪んでいるのです。読者は、不完全な視界の中で作中世界を眺めることになります。
登場人物たちがほんとうはどんな性格をしているのか、話の本質はどこにあるのか。主人公の視界が曇っているために、これらを把握することがきわめて難しくなっています。
その結果、作品を理解することがとんでもない難易度に達しているのです。
これはドストエフスキー中期の小説『賭博者』と同じ構造ですね。『未成年』はそれをより大きなスケールで再現しようとしたのでしょう。
暗示ばかりで読みづらい
それにしても本作の読みづらさは異次元です。すべてが暗示で語られる、異常としかいいようのない形式。
ドストエフスキーはもともとこういう語り方が多いですよね。
たとえば『カラマーゾフの兄弟』でみられる、イワンとスメルジャコフのあいだのやり取り。あれなんか暗示ばかりで難しかったかと思います。
『未成年』の場合、作中のすべてがそういう暗示のレベルで語られているといってもいいでしょう。まさに暗示の糸で織られた作品です。いくらなんでも異常すぎて、これを書いた作者の精神状態が正常だったとはとても信じられないほどです。
『未成年』はどのように評価されてきたか
ドストエフスキーの『未成年』は、文学者からの評価も低かった模様。
ただ、以下のような人物が一定の評価を与えています。
まず代表的なのは、やはりロシア文学研究者のミハイル・バフチン。
彼は『ドストエフスキーの詩学』において、ドストエフスキーの特徴であるポリフォニーの観点からこの作品を論じ、登場人物たちがそれぞれ独立した意識をもって語ることに注目しました。
『未成年』における主人公アルカージーと父ヴェルシーロフの対話も、単なる作者の思想の代弁ではなく、独立した声として分析しています。
バフチンにとって、このような構造は後の『カラマーゾフの兄弟』に通じるものであり、作品の思想的可能性を評価する根拠となりました。
また、日本のロシア文学研究者である米川正夫は、『未成年』をドストエフスキーの思想的変化の鍵として重要視しました。
米川は、この作品において父子関係の葛藤や青年の孤独が深く描かれている点に注目し、表面的なプロットの混乱を超えて、精神的・宗教的テーマを読み取ることができると論じています。
さらに、英語圏の研究者ではジョセフ・フランクが注目に値します。
彼は5巻にわたるドストエフスキーの評伝において、『未成年』を失敗作としつつも、ドストエフスキーの思想的発展の文脈において重要な位置を占める作品であると評価しています。
とくに、信仰、父性、ロシア社会に対する理想と幻滅といった主題が深く掘り下げられている点に注目しました。
ドストエフスキー自身も、『未成年』についてかなり複雑な思いを抱いていたようです。
彼の手紙や回想からは、この作品に対する自己批判的な態度と、それでもなおそこに込めた思想的な意図の両方が読み取れます。
まず、彼は執筆中からこの作品に苦しんでいたことが知られています。金銭的な問題や雑誌連載という制約のなかで、構想を練る余裕もなく、書きながら展開を探るような状態だったと手紙で述べています(もっとも、ドストエフスキーはほとんどの作品をそのような状態で書いているのですが)。
また、予定よりも長くなりすぎてしまったこと、登場人物が増えすぎたことなどにも言及していて、本人も構成の不備を自覚していたようですね。
しかし一方で、彼はこの作品に非常に私的な思いを込めたとも述べています。
とくに、主人公アルカージーに対しては、若き日の自分を投影していたとも言われています。アルカージーの理想主義、誇り高さ、孤独感、そして父への複雑な感情は、若きドストエフスキー自身の心情と重なる部分があると見なされています。事実、彼は手紙の中で、「この作品は私のもっとも個人的な本である」と語っていることがあります。
さらに、『未成年』は、のちの『カラマーゾフの兄弟』に至る構想の一部であるという認識も本人にありました。つまりこの作品を一つの完結した物語というよりも、自身のより大きな思想体系を形にするための予備的な実験として捉えていたふしがあります。
要するに、ドストエフスキーは『未成年』に対して創作的な満足感を持ってはいなかったものの、それでもなお自分にとって本質的に重要なテーマを探求する場であったと考えていたようです。
ドストエフスキーのおすすめ作品は以下の記事でまとめて解説しています↓