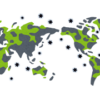神が解説する死後の世界 ニール・ウォルシュ『神へ帰る』
ニール・ドナルド・ウォルシュの「神との対話」シリーズ。
アメリカ人のニールが文字通り、紙面上(本作はパソコンのブラウザ上か?)で神と対話する作品です。
そしてシリーズ最終巻が本書『神へ帰る』。個人的にこれがシリーズ最高傑作だと思います。
というか、僕が知ってる本のなかで、本書ほど強烈なものはほかにないかも(あるとすればシュタイナーあたりか)。
本書のテーマは「死」です。
人は死んだらどうなるのか?ニールとのフランクすぎるほどフランクな対話を通じて、それが事細かに神によって語られていきます。
本書では人が死について学ぶべきこと(正確には思い出すべきこと)として、次の18点が挙げられます。
1 死とは、あなたが自分のためにすることである。
2 あなたの死を引き起こすのは、あなた自身だ。いつ、どこで、どんなふうに死ぬのであっても、これが事実だ。
3 あなたは自分の意思に反して死ぬことはない。
4 「わが家」に帰る道のなかで、ほかの道よりとくに良い道はない。
5 死は決して悲劇ではない。死はつねに贈り物である。
6 あなたと神はひとつである。両者のあいだに分離はない。
7 死は存在しない。
8 あなたは「究極の現実」を変えることはできないが、それをどう経験するかは変えられる。
9 「すべてであるもの」が「自らの経験」によって「自らを知ろう」とする欲求。それがすべての生命・人生の因だ。
10 生命は永遠である。
11 死の状況とタイミングはつねに完璧である。
12 すべてのひとの死は、つねにその死を知るほかのすべてのひとの課題に役立つ。だからこそ、彼らはその死を知る。したがって「無益な」死は――生も――ひとつもない。誰も決して「むだ死に」はしない。
13 誕生と死は同じことである。
14 あなたがたは人生・生命においても死においても、創造行為を続けている。
15 進化に終わりなどというものはない。
16 死から引き返すことができる。
17 死んだら、あなたがたは愛するひとすべてに迎えられるだろう。あなたより前に死んだひとと、あなたより後に死ぬひとたちに。
18 自由な選択は純粋な創造行為であり、神の署名であり、あなたの贈り物であり、あなたの栄光であり、永劫のあなたの力である。
(ニール・ウォルシュ『神へ帰る』吉田利子訳)
これを見ただけでなんかとんでもない内容なんだろうなというのは伝わるかと思います。
そして実際に読んでみると、予期した以上にすごいことが色々と書かれています。
以下、注目ポイントをいくつか概観してみましょう。
死の直後に体験する3つのステップ
人は死ぬとどうなるのか。
本書で神は、死の直後の経験として、まず次の3つの段階を説明しています。
・第1段階 死んでも自分という存在が続いていることに気づく
・第2段階 死後に起こるだろうと信じていたことを体験する
・第3段階 神と対話する
死者はまず自分が信じていた死後の世界を創造する
この第2段階、まずこれが非常に興味深いです。
死者は自分が信じていたものを体験するというんですね。天国があると信じていれば天国を、地獄があると信じていれば地獄を経験する。キリストが迎えに来てくれると信じていればキリストが迎えに来てくるし、仏陀が迎えに来てくれると信じていれば仏陀が迎えに来てくれる。
エベン・アレグザンダー医師が臨死体験について語った『プルーフ・オブ・ヘブン』という名著があります。
そのなかで彼は「自分は他の臨死体験者と違って、先に逝った家族に取り巻かれることがなかった」と怪訝に思っていましたが、それもこれで説明がつきます。
エベン医師は唯物論者だったので、その通りの死後の世界、つまり無を創造してそれを体験したんですね。
またここを考えると、プロの聖職者(牧師とか僧侶とか)の重要性にも思い当たります。
彼らは死の間際の人に対して語りかけ、安心させることを職務として行いますよね。
あれは死の不安を和らげているだけではないんですね。死んでいく者たちが死の第2段階でより良いあの世を創造できるように、手助けしている面もあるんだと思う。放っておいたら「自分は悪い人間だ」みたいな思いのまま、死の第2段階で地獄を創造してしまうかもしれないから。
聖職者たちがそれを意識していることは稀でしょうけれども、本書の内容が事実だとすれば、彼らの行動にはそうした機能もあるのだと思います。
神から「もう終わりにするか」と問いかけられる
次に死の第3段階ですが、この話も初耳すぎる。
死の第2段階が終わったら(気が済むまで第2段階は続くとのこと)、神との対話が始まるといいます。
そして神に「もう終わりにしますか」と聞かれる。何が初耳かというと、ここで「いいえ、まだ終わりにしません。人生に戻ります」という選択ができるらしい。
実際、本書の著者ニールはこの人生で4回死んで、そのたびごとに引き返してきたといいます(本人は覚えてない)。しかもかつてのニールは地獄を信じていたため、死後の第2段階で地獄を体験したこともあったそう。
輪廻転生するとか臨死体験をして戻ってくる人がいるとかはありふれていますが、ほとんどの人が一生のうちに何度か死ぬというのは初めて聞きました。
ちなみに前述のエベン・アレクサンダーも、この第3段階=神との対話を経験しています。安心感に満ちた真っ暗な空間で神と対話をし、真実を知ったと。彼によると神はパーソナル(人格的)な存在で、ユーモアすら持ち合わせていたとのこと。
第3段階以降も色々と想像を絶する事態が待ち受けている模様。
魂は向こうの世界ですべてと一体化し、やがて(といっても時間は存在しないのですが)また地上に向かい、知を体験へと変える欲求に目覚めるようです。
ここからわかるように、本書において神は輪廻転生を完全に肯定しています
人は生まれると身体と精神と魂の3つに分解する
本書によると、人間は3つの層からなるそうです。潜在意識、意識、超意識。
しかしこの世に生まれ落ちることで、この3つが分裂するのだと。
意識がわれわれのいう「自我」のこと。われわれが「自分」とか「私」とかでイメージしているのはこの自我ですね。
しかし実際には、人は潜在意識、意識、超意識の統合体というのが真実。
この3つがズレることなく統合された状態が超絶意識とよばれ、マスター(悟りを開いた人たち)はこれを実現している人のことをいいます。イエスとか仏陀とかですね。
宗教的次元でいわれる「自分」とか「ほんとうの私」とかは、この3つの統合体のことにほかなりません。
この超絶意識の観点からすると、世界は完璧であり、この世に善も悪も存在しないといわれます。
これこそが道徳とは次元の違う宗教の崇高さであり、また同時にその怖ろしさ、ある種の「非社会性」のもとですね。
しかしわれわれの「意識=自我」の観点からすると、やはり世界は理不尽としか言いようがないですよね。
すべてが自分で選択したことだと言われても、正確にはそれは超意識主導の選択なんですよね。自我からすれば「おいおい聞いてないよ」って感じになる。
地上で七転八倒するのはわれわれ自我なわけですが、神やわれわれの超意識たち、もっとお手柔らかに頼むよって感じです。
ちなみに本書によると、幼くして(あるいは生後直後に)死んだ子供はすべて、高位の魂をもった存在とのこと。
自分で達成すべき課題のためでなく、他者の課題に役立つためだけにこの世に姿を現した、高位の存在だと言及されています。
死はエキサイティングな出来事だけど…
この『神へ帰る』ですが、全体的には明るい内容といっていいと思います。
神は死のことを「死はほんとうにエキサイティングでワクワクする事態だよ」みたいに言っていますが、実際そういう気持ちが芽生えてくる人が多いと思う。
ただおそらく例外はあって、「この自分」が消失することに恐怖を感じるタイプの人(西洋人に多い)は、本書を読んでもあまりなぐさめられないかもしれません。
どうしてかというと、死後の自分と今の自分が、今日の自分と昨日の自分のようにつながっているかは疑問だからですね。
むしろ昨日見た夢のなかの自分と、目覚めた今の自分の関係に近いと思われます。
夢のなかの自分はどこへ行ったのか?目覚めた今の自分からしたら、消えてしまったに等しいですよね。
おそらくあの世で目を覚ました本当の自分は、人生を生きているこの今の自分を、まさに夢の中の出来事のように思い出すのでしょう。
その場合、人生を生きている今のこの自分は、やはり夢のように消えてしまうというのが適切かと思います。
また、輪廻が永遠に続くという話も人によって印象が変わりそうですね。輪廻から抜け出して無へ至りたいと感じるひとも、少なくないと思います。
ただしこのような恐怖や不安は、限られた視点から生じる錯覚なのでしょう。リアルなものではないのだと推測できます。
それからドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』でイワンが述べるような「個と全体」の問題は、やはりこのシリーズにおいても鳴り響いています。
要するに「夢の中の個に人権はないのか」みたいな話ですね。最終的にハッピーエンドが訪れるにしても、この苦しみや不幸を受け入れたくはないというような。
たとえば清廉潔白な人間がひどい事件に巻き込まれて、非業の死をむかえたとする。全体としてみればその死には意味があり、また本人の魂も死後の世界でそれを理解している。
しかしそれでも、夢の中においてその苦しみは当人(自我)にとってリアルだったわけですよね。その苦しみは、チャラにしてしまえるのだろうか?
たぶん死んだら(イワンも含めて)みんな納得するんでしょうけれども、夢のなかにいるあいだは、一部の悟りを開いた人間以外には無理ですね。
「神との対話」シリーズは対話だからおもしろい
社会学者のマックス・ウェーバーは、預言者を2つのタイプにわけました。ひとつは倫理的預言者、もうひとつが模範的預言者です。
倫理的預言者というのはユダヤ・キリスト教の預言者あるいはイスラム教のマホメットのように、神から言葉を聞いてそれを伝えるタイプです。
一方で模範的預言者は、ブッダのように、悟りを開いて自分の経験を教えるタイプ。
「神との対話」のウォルシュは、もろに前者ですよね。エックハルト・トールみたいに悟りを開いてその体験を語るというのでなく、ごく普通の人が神からの語りかけを伝達しているのですから。
まさに聖書に登場するような預言者のような存在なわけで、東洋人からするとこういうタイプはかなり珍しく思えます。
そして重要なのは、ニールが神との対話をそのまま掲載している点です。読者はニールの一人称の語りではなく、ダイアローグを読むことになるんですね。
これが本書のおもしろさのカギだと思います。
神の言葉が上から降ってくるみたいな形式では書かれていないわけです。むしろしょっちゅう、ニールが神にツッコミを入れる。
それはおかしい、納得できん、もうやってられんみたいに。
これが劇的な効果を生み出し、本シリーズを比類のない存在にしていると思います。