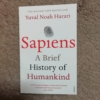聖書の背後にある本当の歴史『聖書時代史』
旧約聖書に書かれているユダヤ人の歴史はどこまで本当なのか?
このような疑問に答えてくれる本が『聖書時代史 旧約編』(岩波現代文庫)です。
歴史学や考古学が明らかにした最新の発見をもとに、旧約聖書の背後にある真の歴史を明らかにする本。
旧約聖書の副読本として最強の効果を発揮します。
異様に面白い本ですが、旧約聖書を読んだことがないと楽しめないかも。聖書をまったく知らない人だと、パレスチナ地方の地味な歴史ぐらいにしか思えない可能性はあります。
旧約聖書を読んで「わけわからん」という思いをした後に読むからこそ、楽しめるのかもしれないですね。色々な謎が氷解して、点と点がつながっていく快感があります。
世界史の知識もあったほうがいいかもしれないです。とくにアッシリア、ペルシア、マケドニア、ローマ帝国あたりの知識ですね。ユダヤ人を翻弄する大国たちです。
これら大国の歴史とユダヤ人ないしは聖書って、頭の中でいまいち結びつかなくないですか?
たとえばユダヤ人がローマ帝国に支配されたとか、アレクサンドロス大王が広めたギリシア文化の影響下でユダヤ人たちが活動したとか聞くと、なんだか意外な気がする。
しかし本書を読むと、ユダヤの歴史が世界史にガッツリと組み込まれます。バラバラだった宗教史の知識と世界史の知識がドッキングする感じ。ここにも快感がありますね。
本書と並行してヨシュア記、士師記を読んでいました。
10年ぐらいいまえに初めて旧約聖書を読んだときは「わけのわからん地味な歴史(というか物語?)だな」としか感じませんでしたが、『聖書時代史 旧約編』で得た知識をベースにして読むと、驚くほどスムーズに内容を理解できます。
旧約聖書がどうにも理解できんという人は、このように視点を変えて歴史学的な方向から攻めるのもありだと思います。
ローマ帝国とキリスト教『聖書時代史 新約篇』
こちらは同じシリーズの新約聖書編。
旧約篇が面白かったので、こっちも読んでみました。期待通りの面白さ。
想像以上にローマ帝国史ががっつり語られます。ユダヤ教やキリスト教に直接関係しない部分もガンガン描写される。本書の半分くらいはローマ史の記述じゃないでしょうかね。
ユダヤ・キリスト教だけに関心のある人は「なぜ自分はローマ史をこんなにがっつり聞かされているんだろう」と思うかもしれません。
しかし自分にはぴったりの本でした。ユダヤ人たちやキリスト教の歴史を、ローマ帝国と結びつけたいというのが要求だったので。何故かわかりませんが、ローマ帝国とユダヤ・キリスト教の歴史が、頭のなかで上手いことリンクしないんですよね。本書を読むとそこが改善されます。
ただし扱っているのは五賢帝の時代までで、コンスタンティヌス以降の国教化の流れなどは別書にあたる必要があります。
ユダヤ人の観点からその後の歴史をたどるならポール・ジョンソンの『ユダヤ人の歴史』、キリスト教のその後をたどるならジャン・ダニエルーの『キリスト教史』あたりが鉄板です。
ユダヤ人というと、超大国から虐げられたか弱い民族みたいなイメージがあるかと思います。少なくとも僕はそういう印象でした。しかし本シリーズを読んでみると、そのイメージがだいぶ訂正されますね。実際にはかなり好戦的で、大国相手に何度も反乱を企てているんですよ。
そしてそのたびごとに壊滅的な敗北を喫している。この人たち何度絶滅してるんだと思うほどです。日本でいう第二次大戦みたいのが何回もある感じですね。
とくに重要なのがネロ帝の時代(紀元60年代)に起こった第一次ユダヤ戦争。ローマ帝国相手に大戦争を行いますが、敗北。エルサレムの神殿体制は崩壊します。
ここでキリスト教がユダヤ教から独立する機運が加速したらしい。ユダヤ教はユダヤ教で、現在の姿につながる改革へと向かいます。
ユダヤ人たちは戦争難民となり散逸。ある方向に散ったグループが後にマタイ福音書をまとめ、また別の方向に散ったグループが後にルカ福音書をまとめ、という流れになっているようです。
本書では「ユダヤ教イエス派」という名称がたびたび用いられます。
イエスがキリスト教徒ではなくユダヤ教徒だったのは常識ですが、どうもパウロでさえ自分をキリスト教徒だとは思っていなかったらしい。その頃はキリスト教など存在せず、イエスを救世主と信じるユダヤ教の分派があったにすぎないんですね。
しかし両者の分離は徐々に進み、第一次ユダヤ戦争でそれが加速します。
ここでキリスト教徒たちが自らのアイデンティティを確立させるために打ち出したのが、福音書とパウロの手紙だった模様。ちなみに、意外なことですが、パウロの手紙は福音書よりも古い文書です。
パウロといえば信仰義認論。律法に従うことでなく、ただ信仰によって人は救われるのだと説く教えです。ユダヤ教は律法を大切にしますから、パウロのこの思想は非常に過激なんですね。
言いかえれば、ユダヤ教とは違うキリスト教のアイデンティティとしてこれはうってつけなのです。だからキリスト教の自立化のために、後代の者たちにパウロ書簡が再利用されたというわけです。
なぜ聖書は正典になれたのか『旧約聖書の誕生』
聖書時代史と同じようなジャンルの本に『旧約聖書の誕生』(ちくま学芸文庫)があります。こっちも勢いで読破してみました。
正直あまり読みやすい本ではなかったです。なんというか「資料」という感じ。文章もぎこちなく(外国語を学習しすぎた弊害か)、読み物としての魅力は薄い印象。
見かけに反して『聖書時代史』のほうが読み物としての面白さは上ですね。岩波現代文庫の装填からしていかにも地味そうな印象を与えますが、実際にはあちらのほうが面白いです。キャッチーなカバーの本書のほうが読むのはきつい感じ。
本書の魅力としては、随所に著者オリジナルの考察が登場する点が挙げられます。
エズラが律法の形式としてわざわざ物語を選んだのは、将来における正典の拡張性を担保するためだったのではないかなど、興味深い指摘が色々となされます。
もっとも興味深かったのが、聖書が正典になれた理由を考察するパート。
聖書のコア部分が編集されたのはバビロン捕囚がペルシア帝国によって解消された直後です。エズラの指揮のもとで、コアとなる部分がまとめられました。なんか聖書というと限りなく昔のテキストみたいな印象がありますけれども、実際にはわりと最近できたものなんですね。
それ以前にも重要な文書はありましたが、正典の地位を占めるものはなかったのです。それら重要な文書をエズラらが編集して、聖典を作った。そして、それがいともたやすく正典になったというわけです。
著者が注目しているのは、エズラがペルシア帝国の高官だった点です。
実は正典はユダヤ民族が自発的にこしらえたものではなく、ペルシア帝国の命令のもとでまとめられたのでした。
ペルシア帝国は支配下の民族にそれなりの自治を認め、その秩序を確かなものとするためにそれぞれの掟を作らせた。そしてその掟を編集するために遣わされたのが、ペルシア帝国の高官にしてユダヤ人のエズラだったのです。
著者はここから、聖書の核となる文書があまりにもスムーズに正典になれた理由として、ペルシア帝国の権威を挙げています。外部の権威が正典の正当性を担保するという、非常に興味深い事態を推測しているのですね。
このロジックどこかで見たことあるなと思ったのですが、これ戦後日本の憲法ですね。
柄谷行人は『憲法の無意識』のなかで、「戦後日本憲法は外部から無理やり押し付けられた、だからこそそこには通常ではありえなかった尊さが発動するようになった」みたいなことを言っていました。
普通であれば、「戦後日本は憲法を外部から押し付けられた、だからダメなんだ」的な理解になりがちですよね。その発想を逆転させているわけです。
最初聞いたときは「ふーんアクロバティックなロジックだな」ぐらいにしか思わなかったのですが、『旧約聖書の誕生』を読んでその話を思い出し、印象が変わりました。外部の権威から半ば押し付けられたからこそ、強大な聖典をもつことができる。これをユダヤ人の歴史は証明している可能性があるんですよね。
だとしたら、戦後日本憲法でも同じ効果が発動してもおかしくはないのかもしれないですね。
他の宗教学の良書は以下の記事を参考のこと。