翻訳の勉強におすすめの本4選【翻訳術からトライアル攻略まで】
学校英語をやみくもに頑張るだけでは、翻訳者にはなれません。
翻訳は、学校でやらされる「英文和訳」や「和文英訳」とはまったく異なるスキルを要求されるからです。
それはどのようなスキルなのか?どうやったら習得できるのか?
一番いいのはプロから直々に指導してもらうことですが、それはなかなか気楽にはできません。
ということで、一流の翻訳者が書いたテキストを頼っていきます。
さいわい現在の日本では良質な翻訳トレーニング本がたくさん出ていますから、修行のための教材に困ることはありません。
翻訳のスキルを伸ばしたいという人のために、僕が使ったことのあるテキストのなかから特におすすめのものを紹介します。
安西徹雄『英文翻訳術』
王道中の王道テキスト。たぶん翻訳術の本のなかでいちばん有名なものです。著者は英文学の教授で、シェイクスピア研究の第一人者でもあります。
英文を引用してきて、著者がそれを訳す。そして訳出に使ったテクニックをことこまかに解説する、という流れ。
英文のレベルはかなり高いですが、解説はむちゃくちゃわかりやすいですよ。実践的な翻訳テクニックがバンバン紹介されていきます。
この本を最低でも2周することをおすすめします。翻訳の基礎力が身につき、学校英語の英文和訳の段階から卒業できるでしょう。
中村保男『英和翻訳表現辞典』
次はこれ。文字通り、820ページの分量を誇る辞典です。しかしただの英和辞典ではなく、一流の翻訳者である著者が長年かけて編み出した翻訳表現を紹介していくという、おそろしいテキスト。
「こんな訳しかたするのかよ」という発見が無数にあります。正解の訳語を見つけるための本ではなく、いわば翻訳脳を磨き上げるための本ですね。
それぞれの英単語につき、かならず例文を引っ張ってくる構成もグッド。例文のなかで単語とその訳出を理解できます。
また、日本語の勉強になる点もポイントです。
翻訳は外国語以上に母国語の能力が重要だといわれますが、日本語力を磨くにはすぐれた日本語を読むしかありません。
本書における著者の訳文はすばらしく、すぐれた日本語のモデルとして機能します。したがってこの辞典を読んでいけば、おのずと日本語力も上がるのです。
英語力や翻訳力のみならず、日本語力もレベルアップできる名著。
近藤哲史『トライアル現場主義!売れる翻訳者へのショートカット』
これは一風変わったテキスト。トライアルに焦点を当てた本です。
トライアルというのは、企業が翻訳者に課す実力判定テストのこと。翻訳の仕事を受注するときには、ほぼ確実にトアイアルを受けることになります。
クラウドワーキングの形態で働く場合でも、最初に安めの報酬でテストを課されると思います。

本書はそのトライアルを課す側の人間がトライアル攻略について解説するという、面白い本。
実際の課題文とその訳例の添削を通じて、どのような文章がトライアルに合格できるのか、ことこまかに解説されます。
この本に書かれたテクニックを知っておくだけで、だいぶ結果が違ってきますよ。
トライアルを課す側は「頼む受かってくれ!」と思いながらテストを出しているのだ、という記述があまりに印象的。これを知っているだけでもだいぶ気が楽になります。
実川元子『翻訳というおしごと』
こちらは翻訳者としていかに生きていくかを指南する本。翻訳業界の動向を知るうえでも役に立つ本です。
出版翻訳、実務翻訳、映像翻訳のそれぞれについて現状と今後の見通しが語られます。
そのうえで、フリーランスとしていかに働いていくのがベストなのか解説されます。
英語勉強法についてもさらっと記述あり。
Amazonプライムの会員になれば無料で読めます(無料体験中に読み切ればOK)。Primeリーディングでダウンロード可能です。
この手の本としては、従来なら山岡洋一の『翻訳とは何か 職業としての翻訳』が名著でしたが、新しい動向まで捉えておくためにはこの『翻訳というおしごと』がオススメです。
独学には翻訳者ネットワーク「アメリア」もおすすめ
翻訳の勉強を始めたばかりの段階では、アメリアに登録するのもおすすめです。
アメリアは翻訳会社フェローアカデミーを母体とする翻訳者ネットワーク。
毎月テキストが送られてきて、課題文を提出すれば添削も受けられます。よい成績を出してクラウン会員になれば仕事を獲得することも可能。
初学者の人が学習ペースをつかむのに最適なサービスですね。
ご利用企業数600社以上 年間の求人件数1,500件以上 翻訳の仕事探しは「アメリア」★「レストランレビュー翻訳コンテスト」のコンテスト会員登録で入会金0円。5/16まで
アメリアについては以下の記事でもくわしく解説しているので、参考にしてみてください。
他に必要な学習は?
以上の本や教材を利用すれば、基礎的な翻訳スキルが身につきます。正確な理解力、的確な表現力、流暢な文章作成力ですね。
しかし翻訳の勉強はそれだけで十分かというとそうでもないです。とくに次の2つが重要です。
・多読と多聴で外国語力を向上させる
・専門知識をつけて日本語の運用能力を洗練させる
多読・多聴で外国語力を向上させる
外国語の能力を上げるためには、翻訳トレーニング本の精読だけでは不十分です。量を稼ぐことを主眼とした学習も必要になってきます。第二言語習得研究によると、外国語学習でもっとも重要なのは大量インプットですので。
これを達成するのが多読と多聴です。
洋書とオーディオブックを利用してどんどんインプットを増やすのがおすすめ。インプットというとリーディングが思い浮かぶかと思うんですが、多聴でも同様の効果はあります。
自分の専門フィールドに近い本を読むのがコツです。こうすれば一般的な外国語力が伸びると同時に、自分の翻訳分野に必要な単語や言い回しにも馴染めます。
専門知識をつけて日本語の運用能力を洗練させる
翻訳には専門的な知識が必要です。読解に必要という以上に、表現するときに必要なんですよね。
例えば金融の分野だとfallが「弱含む」になったり、continue to riseが「続伸する」になったりします。簡単に訳せる単語でも、こういう専門的な言い回しには知識がないと対応できないですよね。
そのジャンルに特有の言い回しを身につけるには、外国語の多読多聴だけでは不十分。ここでは日本語でのインプットが重要になってきます。
したがって自分の翻訳ジャンルの書籍やサイトなどを、日本語で日常的に読むようにするのがおすすめです。
音読や写経も効果があります。外国語を音読したり書き写したりするのはよく実践されることですが、翻訳者の場合は母国語でもこれをやる人が多いです。
翻訳学習におけるノート活用術
翻訳の勉強でノートをどうやって使ったらいいのかというのもけっこう多い質問なので、答えておきます。
ノート活用術は次のようなものがあります。
・単語帳(表現辞典)を作る
・翻訳のミスを記録する
・写経する
単語帳(表現辞典)を作る
一番の王道はノートを単語帳にするというもの。
普通の辞書に載っているような単語は記録しなくていいです。辞書にないようなめちゃくちゃ専門的な単語を記録していきます。
あるいは単なる英和・和英辞典ではなく、翻訳表現辞典にするのもおすすめ。この場合は普通の辞書に載っている単語も記録しますが、普通の訳ではなく、翻訳としてのクオリティが高い「意訳」を記録していきます。
できれば例文ごと書き写しておくのが望ましいです。
翻訳のミスを記録する
誤った訳を記録しておくのも学習効果が高いです。もちろん正解のほうも併記しておきます。
今後、同じような間違いを繰り返す確率が減ることでしょう。自分自身の成長を振り返ることもできます。
写経する
お手本となる文章をひたすら書き写していきます。
外国語への翻訳を生業にするなら外国語を写経し、日本語への翻訳を生業にするなら日本語を写経します。
このとき音読しながら書き写すとさらに効果がアップします。
この3つがノートの代表的な活用術です。
まとめ
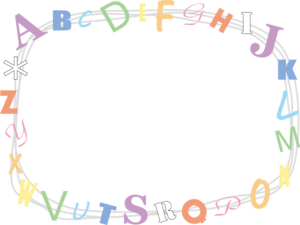
以上、翻訳トレーニングにおすすめの本の紹介でした。
・安西徹雄『英文翻訳術』
・中村保男『英和翻訳表現辞典』
・近藤哲史『トライアル現場主義!売れる翻訳者へのショートカット』
・実川元子『翻訳というおしごと』
また翻訳学習書に取り組む以外にも次の学習が重要です。
・多読と多聴で外国語力を向上させる
・専門知識をつけて日本語の運用能力を洗練させる
ノート活用術は次の3つが代表的なものでした。
・単語帳(表現辞典)を作る
・翻訳のミスを記録する
・写経する
独学には翻訳者ネットワーク「アメリア」もおすすめです。
ご利用企業数600社以上 年間の求人件数1,500件以上 翻訳の仕事探しは「アメリア」★「レストランレビュー翻訳コンテスト」のコンテスト会員登録で入会金0円。5/16まで
![]()
アメリアについては以下の記事も参考にしてみてください。

















