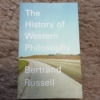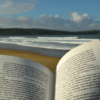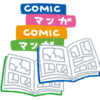西洋哲学の根源はギリシア哲学とヘブライ宗教『ヨーロッパ思想入門』
岩波ジュニア新書を代表する名作のひとつ『ヨーロッパ思想史』。
著者の岩田靖夫は古代ギリシア哲学を専門とする大物です。彼が10代の学生向けに書き下ろした新書がこの本。
岩波ジュニア新書といえば遅塚忠躬の『フランス革命』がパッションのほとばしる名著として有名ですが、本書もそれに勝るとも劣らない本だといえそう。
本書の特徴は、ヨーロッパ思想の根源に注力し、そこをピンポイントに語る構成にあります。
ではヨーロッパ思想の根幹とはなにか?
ギリシア哲学とヘブライの宗教(ユダヤ教およびキリスト教)です。

著者は次のように言っています。
ヨーロッパ思想は二つの礎石の上に立っている。ギリシアの思想とヘブライの信仰である。この二つの礎石があらゆるヨーロッパ思想の源泉であり、二〇〇〇年にわたって華麗な展開を遂げるヨーロッパの哲学は、これら二つの源泉の、あるいは深化発展であり、あるいはそれらに対する反逆であり、あるいはさまざまな形態におけるそれらの化合変容である。
(岩田靖夫『ヨーロッパ思想史』)
本書は全体で約240ページの本ですが、ギリシアとヘブライだけで150ページを費やしています。ヨーロッパを準備したヨーロッパ以前の初期の思想に、大半のページが費やされるという大胆な構成。
ギリシアの思想
第一部はギリシアの思想です。
哲学だけでなく、ホメロスやギリシア悲劇(アイスキュロス、ソフォクレス)までをもかなりくわしく取り上げています。ギリシア民族全体の精神的傾向性を浮かび上がらせようとしている感じ。
哲学の分野で取り上げられるのはクセノパネス、パルメニデス、デモクリトス、プロタゴラス(この人はソフィストと言われますが)、ソクラテス、プラトン、アリストテレスです。
ソクラテスは自然学に絶望し、人々との反駁的対話というロゴスの道によって「善」の探求へ向かったという。あらゆる知識の根底に「善」についての認識がなければならないというソクラテスのこの考えは、いわば、理論理性に対する実践理性の優位を主張する革命的な思考の転換だった。
(同書より)
ヘブライの信仰(ユダヤ教とキリスト教)
第二部はヘブライの信仰が解説されます。何気にこのパートがいちばん熱い。
最初にイスラエル人の歴史をざっと概観。次に旧約聖書の解説に移ります。
旧約聖書で取り上げられるのは『創世記』。それからアモス、ホセア、第2イザヤの預言者が解説されています。
第二部の後半がキリスト教についての解説。
まずはイエス・キリストが取り上げられ、最後にパウロの解説がきます。パウロはキリスト教徒たちを迫害するユダヤ教徒でしたが、ある日まばゆい光に襲われて、一瞬で回心します。
後にわれわれが知るような形のキリスト教を作り上げたのはこのパウロでした。
ちなみにヘブライの信仰に興味のある人には岩波現代文庫から出ている『聖書時代史』がおすすめです。
ヨーロッパ哲学のあゆみ
第三部でようやくヨーロッパ哲学が語られます。
取り上げられるメンバーは以下の通り。
アウグスティヌス
トマス・アクィナス
デカルト
カント
ロック
ロールズ
キルケゴール
ニーチェ
ハイデガー
レヴィナス
目を引くのはロールズとレヴィナスですね。これだけざっくり語るなかに、このふたりが入るのかという。それだけ著者の思い入れがある哲学者なのでしょう。
ロールズは20世紀アメリカの政治哲学者で、「正義」の問題を考え抜き、現代リベラリズムの創始者となりました。
レヴィナスは20世紀フランスの哲学者。ハイデガーの存在論を批判し、倫理的な思索(存在者の次元を存在へ解消しないこと)を突き詰めたことで知られます。
キルケゴールやニーチェを大きく取り上げるところにも表れているように、岩田靖夫は倫理学的な思想を軸にするタイプの学者だと思われます。
岩田靖夫の『ヨーロッパ思想入門』はあくまでも西洋哲学のコアをピンポイントに射抜く構成です。
中世以降の解説はほんとうにざっくりしているので、他書にあたったほうがいいでしょう。
哲学史のおすすめ本については以下の記事を参考にしてみてください。
二元論のもたらす豊かさ
このように、ヨーロッパ思想の根底には、理性と論理の伝統であるギリシア哲学と、信仰と啓示の伝統であるヘブライ宗教(ユダヤ教、そしてそこから発展したキリスト教)という、まったく異なる二つの源流があります。
まず、根本的な違いを見てみると、ギリシア哲学は「人間の理性によって真理を探究する」姿勢を持ちます。プラトンやアリストテレスに代表されるように、自然、倫理、政治などあらゆる分野を理性的に解き明かそうとする態度が特徴です。
一方、ヘブライ宗教、特に旧約聖書に示される信仰は、「神との契約」や「啓示による真理」を重視し、人間が理解できるかどうかにかかわらず、神の意志に従うことを善とします。
普通ならどっちかが廃れてしまいそうなものですよね。しかし西洋においてはそうならず、むしろ不思議な共存関係で両者は影響を与え続けます。
その鍵となったのが、キリスト教をギリシア哲学と融合させた初期教父たちや中世の神学者たちの営みです。
たとえばアウグスティヌスはプラトン的な二元論やイデア論を取り入れつつ、信仰を中心に据えました。さらにトマス・アクィナスは、アリストテレス哲学を大胆に取り入れて「信仰と理性は最終的には一致する」と説き、神学と哲学を統合しようとしました。
このように、ヨーロッパ思想の中では、「信仰は理性によって理解されうる」「理性は神の創造の一部である」という考えが発展し、両者の緊張関係は完全な対立には至らず、「信仰は土台、理性は手段」といったヒエラルキーの中で共存が可能となりました。
また、時代によってどちらが強調されるかは変動しています。中世では信仰が優位にありましたが、ルネサンスや啓蒙時代になると、再びギリシア的理性が前面に出てきます。
それでも、たとえばカントやキルケゴールのように、理性と信仰の境界を再検討する思想家が現れることで、両者の伝統は捨てられることなく、むしろ反復されていきました。
ギリシアとヘブライ、この「水と油」のような思想は、一方が他方を単に打ち負かすのではなく、時に緊張し、時に妥協し、時に統合されながら、西洋精神の複雑な層を形づくっていきます。
おそらく、この二元論こそが、後世にまで深い影響を与える「西洋哲学」の奥行きの秘密でもあるのだと思います。