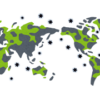ロマン主義が退屈を生んだ スヴェンセン『退屈の小さな哲学』
ノルウェーの哲学者ラース・スヴェンセンが書いた『退屈の小さな哲学』(集英社新書)を読みました。
國分功一郎の『暇と退屈の倫理学』でも取り上げられていた本です。僕はそこで興味をもちました。
現在では手に入りにくくなっている本ですが、僕は運良く中古でゲットできました。
そういえば集英社新書が海外の哲学書を翻訳して出版するのってかなりめずらしい気がします。
退屈論のカタログとして読める
哲学の本ではありますが、形態はエッセイです。
國分功一郎が言っていた通り、スヴェンセンはまさに博覧強記の人。膨大な引用とともに話は進行します。退屈についてのコメントを集めたカタログとしても読めます。というか、そこがこの本の最大の強みかもしれません。
登場するのは以下のような面々。
パスカル
ショーペンハウアー
キルケゴール
ニーチェ
ウィトゲンシュタイン
ハイデガー
ベケット
バイロン
シオラン
スタンダール
ボードレール
トーマス・マン
バラード
ウォーホル
プルースト
あの哲学者はこう言ったとかこの文学者はそういったとか知れるのは楽しいですし、さまざまな偉人たちが退屈に悩まされる姿を見ると、それだけで慰められます。
現代人はロマン主義の子
スヴェンセンによると、退屈は近代以降の現象だそうです(中世日本には兼好法師の徒然草などがありますが、それは置いておきましょう)。
そして退屈誕生の場所を18世紀ドイツのイエナに求めます。
なぜイエナなのか?
当時のイエナではカントやフィヒテの哲学が全盛を誇り、そこからドイツロマン主義という流れが誕生しました。そしてスヴェンセンによると、このロマン主義こそが退屈の生みの親なのです。

この「ロマン主義」というやつ、厳密になにを意味しているのか僕は昔からいまいち掴みかねているのですが、ここでは深堀りしないでおきましょう。
なぜロマン主義が退屈を生むのか?
それはロマン主義のなかにある個人主義的な要素が原因です。近代以前においては、社会が人の一生に意味を与えていました。これに対してロマン主義以降になると、人生の意味は個人が決定するものになる。
しかしそれは不可能なのですね。物事の価値が主観の価値判断にかかっているとなると、物事は空虚になるのです。本書でも参照されていますが、ここはヘーゲルによるロマン主義批判が核心をついています。
「自我や主観が価値や掟を決定する」。カントは無邪気にこう主張しますが、自我を神のポジションに祭り上げることは、そのまま世界の空虚へとつながるのです。
たしかにカントの『啓蒙とは何か』みたいな「自分の頭で考えろ」的な主張には、僕はどうも違和感を覚えるんですよね。そんなに簡単なものなのかなと思う。ヘーゲルによるカント批判はその違和感を言い当ててくれています。
ハイデガーの退屈論『形而上学の根本諸概念』
第三部ではハイデガーの『形而上学の根本諸概念』が取り上げられます。
これはハイデガーが退屈について論じた有名な講義録ですね。スヴェンセンはこの講義録を哲学の最高傑作とまで言っています。
そういえば國分功一郎の『暇と退屈の倫理学』も、ハイデガーのこの講義の読解を中心にすえたものでした。國分はこの本からかなり影響を受けてそう。
ただし哲学の解説書としては國分の本のほうが優れていますね。スヴェンセンによるハイデガー解説はあまりおもしろくないです。
退屈は解決できない…か?
長々と続くエッセイですが、最後は「退屈には解決法がない」という言葉で締めくくられます。
たしかに一般的なレベルではそう結論せざるを得ない気がしなくもない。
でも僕が思うに、悟りを開くというのが一つの解決法としてあると思います。ほとんど非現実的ですが、可能性としては否定できないですからね(難易度としてはたぶん、プロ野球選手になるのと同じくらいの難しさ)。
たとえば本書でも何度も言及される哲学者ショーペンハウアーは、この可能性をその哲学体系のなかに組み込んでいます。
これはショーペンハウアーが宗教的な夢想家だからそうするのではなくて、むしろ経験的事実を重視する性格をもっているからそうするのですね。
現に世界には、悟りを開いて退屈とは無縁な人生を送る覚者が存在しているわけですから。彼ら彼女らを無視して話を進めることのほうが、非現実的な態度だといえるでしょう。