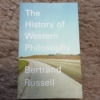アメリカ人の原型『ハックルベリー・フィンの冒険』【書評】
アメリカ文学を代表する存在といえば、マーク・トウェインのハックルベリー・フィン。
名前しか聞いたことがありませんでしたが、今回初めて読みました。しかもいきなり原書で挑戦。
先日『トム・ソーヤーの冒険』を読んだら思いの外おもしろかったので、続編にあたる『ハックルベリー・フィンの冒険』も原著で読むことにしたというわけです。
読みやすい本ではありません。というか読みにくいです。
まずハックは口調が独特です。そのうえ相棒として登場するジムは当時の黒人奴隷に特有の英語を話すため、読解が大変すぎる。
英語の勉強のための洋書テキストとして見た場合、本書は『トム・ソーヤーの冒険』に比べて格段に難易度が高いです。ボリュームも多い。
安易に手を出さないほうが賢明かも。原書で読むならトム・ソーヤーのほうをおすすめします。
物語としてはあんまりおもしろくない
物語としてみると、『トム・ソーヤーの冒険』のほうがはるかにおもしろいです。
まあ本書も序盤はおもしろいんですけどね。
まずハックの父親パップのキャラが強烈。アルコール中毒の中年男で、典型的な毒親といっていいでしょう。でもなんだかキャラが立っていて、どこか魅力的。彼が暴れまわる序盤は引き込まれました。
ハックは父親から逃げ出し、筏でミシシッピ川を下ります。途中で黒人奴隷のジムと出会い、彼の逃亡に加担。二人はひたすら南へと川を下っていく。
ここから先は短編小説のような趣。川を下る途中でいろいろな事件に遭遇し、ハックとジムはそれに巻き込まれていきます。
ちょっとRPG感もありますね。指輪物語で川を下るシーンを思い出したりもしました。おそらくトールキン自身も、執筆中にハックルベリー・フィンを想起したのではないでしょうか?
最後はあたかもデウス・エクス・マキナ(機械仕掛けの神)のようにまたしてもトム・ソーヤーが登場。物語を強引に収束させます。
ハックルベリー・フィンとは何者なのか?
この『ハックルベリー・フィンの冒険』という作品、アメリカ近代文学のルーツという評価を受けています。そして主人公ハックは「アメリカ人の原型」と呼ばれる。
たとえばアーネスト・ヘミングウェイは次のように言います。
「アメリカの現代文学はすべてマーク・トウェインの『ハックルベリーフィン』という一冊の本から出発している。…それ以前には何もなかった。それ以降もこれに匹敵するものは何もない」(亀井俊介『ハックルベリー・フィンのアメリカ』p5)
なぜこの作品は、そしてその主人公であるハックはこれほどの評価を受けるのか?
亀井俊介の『ハックルベリー・フィンのアメリカ』(中公新書)を参考にして、その理由を探ってみましょう。
『ハックルベリー・フィンのアメリカ』で亀井は、トム・ソーヤーとハックルベリー・フィンを対比させて論じます。これがおもしろい。
トムは『トム・ソーヤーの冒険』のなかで、幾度となく村からの脱出劇を演じました。
しかしこれは、英雄として帰還することで村のみんなから称賛されることが目的です。つまりトムの脱出は、村への帰還が前提なのです。いくら自然を志向していたとしても、トムはあくまでも文明人だといえます。
一方、ハックの脱出は村への帰還を前提としていません。
彼はただ村やそこに住む人々、もっといえば文明的生活そのものから逃げ出すために脱出を図ります。トムとは対照的に、ハックは文明の子ではなく、自然に帰ることを望む自然児です。
ここには後のアメリカを支配することになる文明と自然の対立というテーマが見え隠れします。
アメリカにおける文明と自然の対立
アメリカの根源には、文明と自然の矛盾が存在しています。
ここでいう文明とは、アメリカ人たちがそこから脱出してきた(あるいはそこから追放された)ヨーロッパ社会を指します。
それに対して自然とは、自分たちがヨーロッパから逃れ出て辿り着いたアメリカ大陸を意味している。
自然への志向、これがアメリカの原点にあるわけですね。だからこそ、自然に帰ることを求めるハックルベリー・フィンがアメリカ人の原型と呼ばれるのです。そして彼の行動はそのまま、文明化するアメリカへの風刺になる。
またトムとハックの対照が、文明と自然の対立を表していることも明らかですね。
文明化と自然の矛盾。アメリカ文学はこれをテーマに数々の名作を生み出していきます。
その端緒となった『ハックルベリー・フィンの冒険』が、アメリカ近代文学のルーツとされる所以です。
『ハックルベリー・フィンの冒険』は風刺小説
『トム・ソーヤーの冒険』は楽しい冒険活劇という感じでしたが、この『ハックルベリー・フィンの冒険』は風刺小説としての色調が強いですね。
たとえばスウィフトの『ガリバー旅行記』あたりに近いものがあると思います。
批評家が本書を持ち上げるのは、この辺に理由があると思われます。
『トム・ソーヤーの冒険』も英語で読んでみた
『トム・ソーヤーの冒険』も原書で読んでみました。文章の読みやすさは圧倒的にこちらが上です。物語としての面白さもこちらに軍配。洋書多読の一環として読むなら断然こっちがおすすめ。
この本を読んでみて驚いたのは、ハックルベリーフィンがばんばん登場するところですね。『トム・ソーヤーの冒険』にハックルベリーフィンが登場することは知っていましたが、ここまで準主役級として登場しまくるとは思っていませんでした。
マーク・トウェインは楽天的な近代主義者として出発したものの、後年ペシミズムに陥り、作風が暗くなったとよく言われます。
しかし本作のハックルベリーフィンの言動を見ると、この頃からすでにそういう傾向は胎動していたんじゃないかと思えますね。
たとえば物語の後半、トムといっしょに財宝を手に入れたハックはお金持ちの夫人宅にかくまわれることになるのですが、その文明的な暮らしに嫌気がさし脱走。連れ戻しに来たトムに向かって彼は次のようにいいます。
Tom, being rich ain’t what it’s cracked up to be. It’s just worry and worry, and sweat and sweat, and a-wishing you was dead all the time. (Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer)
文明のなかで豊かな暮らしをしたって、その内実は心労と苦労の連続。これなら死んでたほうがマシじゃないかというんですね。
『トム・ソーヤーの冒険』のなかで、ハックルベリーフィンのこの台詞がいちばん印象に残りました。