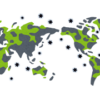イギリス経験論の全体像を解説【ロック・バークリー・ヒューム】
私たちは、見て、聞いて、触れることで世界を知っていく。
こうした「常識的」な感覚は、西洋哲学においては決して当たり前の前提ではありませんでした。プラトン以来の哲学の主流は、むしろ数学をモデルにして、理性のはたらきだけで世界の真実をつかめると考えていたからです。
そこに経験重視の視点をもたらし、それを突き詰めることで哲学に革命をもたらしたのが、「イギリス経験論」なのです。
イギリス経験論は、人間の知識や認識の起源を、理性や生得的な原理ではなく、経験に求めようとする立場です。
しかしそれは、単なる常識的な経験重視ではありません。経験とは何か、経験から何が言えて、何が言えないのかを徹底的に問い詰めた結果、近代哲学そのものの前提が揺さぶられることになります。
経験を信じるとは、いったい何を信じることなのか。その問いが、どこまで私たちを連れて行くのか。イギリス経験論の展開を追うことで、哲学が直面した最も根源的な問題が浮かび上がってくるでしょう。
なぜ「イギリス経験論」と呼ばれるのか
そもそもなぜ「イギリス経験論」と呼ばれるのでしょうか。
それは単に、経験を重視した哲学者がイギリスに多く現れたから、という地理的な理由だけではありません。そこには、イギリスという社会と知的風土が育んだ、独特の哲学的態度があります。
近代初期のヨーロッパでは、理性によって世界の真理を体系的に把握しようとする思想が大きな力を持っていました。
大陸では、
デカルト
スピノザ
ライプニッツ
などに代表される大陸合理論が発展し、確実性や必然性を重んじる哲学が追求されました。
この大陸合理論は、数学を哲学のモデルにしています。
これに対してイギリスでは、抽象的な原理から出発するよりも、実際に人間がどのように世界を経験しているのかを出発点にすべきだ、という考え方が強く支持されるようになります。
イギリス経験論の特徴は、人間の認識をできるだけ地に足のついたものとして捉えようとする姿勢にあります。
私たちの知識はどこから来るのか、心はどのようにして観念を形成するのか、といった問題を、先天的な理性の力に頼るのではなく、感覚や経験の積み重ねから説明しようとします。この点で、「経験(experience)」が哲学の中心概念となりました。
代表的な哲学者は、
ジョン・ロック
バークリー
ヒューム
です。
大陸合理論が数学をモデルにしていたのに対して、イギリス経験論は実験科学を哲学のモデルにしています。
ただ、ここで重要なのは、イギリス経験論が一枚岩の楽観的思想ではないという点です。
経験に基づいて知識を説明しようとする試みは、やがて因果性や自我、外界の存在といった、私たちが当然だと思っている概念そのものを疑う方向へと進みます。
この懐疑的な徹底性もまた、イギリス経験論の重要な特徴であり、大きな魅力です。
「イギリス経験論」とは、ヨーロッパ大陸から海で隔てられた島国の哲学者たちが、経験を認識の基礎に据え、観察・分析・慎重な思考を重ねることで人間の知の限界と可能性を探究した思想の流れを指します。
その姿勢が一貫して共有されていたからこそ、後にまとめて「イギリス経験論」と呼ばれるようになったわけです。
ベーコン:経験論的精神の誕生
フランシス・ベーコンは、しばしばイギリス経験論の出発点として名前が挙げられます。
ただし、彼は後のロックやヒュームのように、人間の認識の仕組みを体系的に論じた哲学者ではありません。ベーコンの意義は、認識の理論そのものよりも、知がいかにして獲得されるべきかという「態度」と「方法」を根本から転換した点にあります。
中世以来、学問の世界ではアリストテレス哲学とスコラ学が大きな権威を持っていました。そこでは、既存の教義や概念体系を前提とし、演繹的な推論によって結論を導くことが重視されていました。
ベーコンはこの学問のあり方を強く批判し、人間はまず自然そのものに向き合い、事実を丹念に観察するところから出発すべきだと主張します。
彼が重視したのが、経験に基づく帰納的な方法です。個々の観察や実験を積み重ね、そこから一般的な法則を慎重に導き出す。この姿勢は、後に近代自然科学の基本態度となります。
ベーコンの思想で特に重要なのが、「イドラ(偶像)」と呼ばれる概念です。
彼は、人間の認識がさまざまな先入観や思い込みによって歪められていることを指摘しました。人間一般に共通する偏見、言語に由来する誤解、伝統的権威への盲信などが、正しい認識を妨げると考えたのです。
経験に基づく知を確立するためには、まずこれらのイドラを取り除かなければならないとされました。
このようにベーコンが打ち立てたのは、完成された経験論の理論ではなく、経験を出発点とする思考の方向性でした。理性の力を否定したわけではありませんが、それを経験から切り離された絶対的なものとして扱うことを拒んだ点に、彼の革新性があります。
ベーコンによって提示されたこの経験論的精神は、後のイギリス哲学に深く根を下ろします。人間の知はどこから来るのか、どこまで確かなものなのかという問いが、抽象的な形而上学から、人間の実際の経験を分析する問題へと引き寄せられました。
こうしてベーコンは、ロック以降に展開されるイギリス経験論の思想的土壌を切り開いた人物として位置づけられるのです。
ロック:穏健な経験論の成立
ジョン・ロックは、イギリス経験論を本格的な哲学理論として成立させた人物です。ベーコンが示した経験重視の精神を、人間の認識の仕組みそのものの分析へと押し進めた点に、ロックの決定的な意義があります。
ロックの出発点は、生得観念の否定でした。
人間は生まれながらにして何らかの観念や原理を備えているのではないか、という考え方は当時広く受け入れられていました。
これに対してロックは、もし生得観念が存在するのであれば、すべての人に明白に意識されていなければならないはずだと論じます。しかし実際には、そのような普遍的に共有された観念は見当たりません。
こうしてロックは、生得観念説を退け、人間の認識はすべて後天的に形成されると主張しました。
この立場を象徴するのが、心を「白紙(tabula rasa)」にたとえる比喩です。人間の心には、あらかじめ書き込まれた内容はなく、そこに観念が書き込まれていくのは経験を通じてであるとされます。
では、その経験とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
ロックは、観念の源泉を二つに分けて説明します。
一つは外界の事物が感覚器官に作用することで生じる「感覚(sensation)」です。色や音、硬さや運動といった観念は、外界との接触を通じて心に与えられます。
もう一つは、心が自らの働きを内省することから生じる「反省(reflection)」です。考える、疑う、信じるといった心の働きそのものもまた、経験として観念の材料になると考えられました。
さらにロックは、外界の性質について一次性質と二次性質の区別を導入します。
一次性質とは、形、大きさ、運動、数といった、事物に客観的に備わっていると考えられる性質です。
これに対して、色や音、味などの二次性質は、事物そのものにあるというよりも、事物が私たちの感覚に及ぼす作用として理解されます。
この区別によって、ロックは経験に基づきながらも、外界の実在を完全には否定しませんでした。
このようにロックの経験論は、経験を認識の唯一の源泉としながらも、日常的な常識世界を大きく損なわない穏健な性格を持っています。外界の存在や科学的認識は基本的に維持されており、極端な懐疑には踏み込みません。
イギリス経験論に地味なイメージがつきまとうのは、出発点としてのロックにあるこの穏健さが原因だといえます。
しかしロックによって幕を開けた経験論は、後のバークリーやヒュームによって、この穏健さが次第に問い直されていくことになるのです。
バークリー:経験論の急進化
ジョージ・バークリーは、ロックによって打ち立てられた経験論を、徹底的に推し進めた哲学者です。
彼の思想は、経験論の内部から生まれた急進的な批判であり、その結果として、常識的に前提とされてきた「物質世界」そのものが揺さぶられることになります。
バークリーの出発点は、ロックの理論に対する疑問でした。ロックは、観念はすべて経験に由来するとしつつも、その背後に「物質」という基体が存在すると考えていました。
しかしバークリーは問います。私たちは、観念以外の何かとして「物質」を経験しているだろうか、と。色や形、硬さといった性質はすべて知覚の中に現れるものであり、知覚から独立した物質そのものを捉えることはできないのではないか、というのです。
この問いから導かれるのが、バークリーの有名な命題、「存在するとは知覚されることである」です。
私たちが存在を語るとき、それは常に何らかの形で知覚されていることを意味します。知覚され得ない物質的基体を想定することは、経験論の立場からすれば余計な仮定にすぎないとバークリーは考えました。
この立場に立つと、ロックが導入した一次性質と二次性質の区別も維持できなくなります。
形や運動といった一次性質も、色や音と同様に、知覚される限りでしか与えられません。知覚から独立して存在する性質を認める根拠はなく、一次性質も二次性質も、等しく心に与えられる観念にすぎないとされます。
こうしてバークリーは、経験論を徹底した結果、物質という概念そのものを哲学から排除します。世界を構成するのは、知覚される観念と、それを知覚する精神だけであり、常識的に考えられてきた「物質世界」は、独立した実体としては姿を消します。
これはしばしば極端な観念論として受け取られますが、バークリー自身は、経験に忠実であろうとした結果にすぎないと考えていました。
この点に、バークリー哲学の最大の見せ場があります。穏健に見えたロックの経験論は、その前提を一つ一つ吟味していくと、常識的実在論を支える足場を失っていきます。経験を唯一の基準とする態度は、ここで一気に形而上学的ラディカリズムへと転じるのです。
イギリス経験論は、バークリーにおいて、もはや「常識の哲学」ではありえなくなりました。
ヒューム:経験論の完成と内部からの崩壊
デイヴィッド・ヒュームは、イギリス経験論を徹底的に推し進め、その可能性と限界を同時に露わにした哲学者です。彼の思想において、経験論は一つの完成点に到達しますが、その完成は同時に、経験論そのものの自己崩壊を意味していました。
ヒュームの認識論の基礎にあるのは、観念と印象の区別です。
印象とは、感覚や感情として直接与えられる生き生きとした経験であり、観念とは、それが心の中で弱められた写しにすぎません。すべての観念は、最終的には何らかの印象に由来していなければならない。これがヒュームの経験論の基本原理です。
この原理に照らしてみると、私たちが当然のように使っている多くの概念が、実は確かな根拠を欠いていることが明らかになります。
その代表例が因果性です。
私たちは、ある出来事が別の出来事を必然的に引き起こすと考えがちですが、経験の中に与えられているのは、単なる出来事の継起だけです。原因と結果を結びつける必然的な力そのものを、私たちは知覚したことがありません。それでも因果関係を信じているのは、同じ種類の出来事が繰り返し結びついて現れるのを見てきた結果、そう期待する習慣が形成されたからにすぎないとヒュームは説明します。
同様の批判は、自我の概念にも及びます。
内省によって見いだされるのは、思考や感情、感覚といった個々の知覚の流れであって、それらを統一する固定的な「自我」そのものではありません。自我とは、独立した実体ではなく、さまざまな知覚が束となって連なっているにすぎない。これがいわゆる自我の束説です。
さらに深刻なのが、帰納の問題です。
過去に観察された規則性が、未来にも成り立つと信じる根拠はどこにあるのか。この問いに対して、経験に訴えることはできません。なぜなら、その正当化自体がすでに帰納に依存しているからです。理性によっても、経験によっても、帰納を合理的に基礎づけることはできない。この点で、科学的知識の根拠そのものが揺らぐことになります。
このように経験論を徹底した結果、ヒュームの哲学では、科学的因果法則、自我の同一性、神の存在、さらには道徳的価値までもが、理性によっては確実に基礎づけられないものとして現れます。
これらは人間の生活においては避けがたく信じられているものですが、その信念は合理的証明に基づくものではなく、習慣や感情に支えられているにすぎないとされます。
ここに、イギリス経験論の到達点があります。経験を唯一の基準として認識を分析し尽くしたとき、私たちが確実だと考えてきた世界像は崩れ落ちます。
この意味で、経験論はヒュームにおいて完成し、同時に破綻しました。だからこそ彼の思想は、近代哲学に深刻な衝撃を与え、次なる哲学的転換を不可避なものとしたのです。
自然科学との不思議な関係
イギリス経験論と自然科学の関係は、一筋縄ではいかない不思議な性格をもっています。
実験科学をモデルに哲学を押し進めたのだから、経験論と科学は相性がよさそうに思えますよね。しかし、実際のことろ、バークリやヒュームは経験論の徹底によって、科学の確実性を疑うところに行きつきます。
どうしてそうなるかというと、岩崎武雄が指摘したように、イギリス経験論の根底にも、合理論的な思考モデルがなお残っていたからです。
合理論はこう考えました。
先天的(経験によらない認識。たとえば数学や論理学)な認識のみが真理をつかめる→われわれの理性にはそのような能力がそなわっている→だからわれわれは真理を理解できる
一方で経験論はこう考えます。
先天的な認識のみが真理をつかめる→しかしわれわれは理性だけではものごとを認識できず、経験という素材が必要である→したがってわれわれは真理に到達できない
出てくる結論は反対ですが、議論の出発点となる前提は同じものを共有しているわけです。
これによって、イギリス経験論と自然科学の関係は、一筋縄ではいかない複雑な性格を帯びることになります。
カントへの継承と近代哲学の転換
イギリス経験論は、ヒュームにおいて一つの極点に達します。経験に基づいて認識を説明しようとする試みは、因果性や自我、外界の存在といった概念の確実性を根底から揺るがし、理性によって世界を確実に把握できるという近代哲学の前提そのものを崩しました。
そして、この懐疑は、単なる行き止まりではなく、次の哲学的転換を準備する役割を果たします。
この転換点に立つのが、ドイツのイマヌエル・カントです。
カント自身が述べているように、ヒュームの因果性批判は彼を「独断のまどろみ」から目覚めさせました。ヒュームは、経験の中には因果関係そのものは与えられておらず、私たちが見ているのは出来事の継起にすぎないと主張しました。この指摘は、カントにとって、極めて深刻な問題を意味します。
カントはこの懐疑を退けるのではなく、真正面から引き受けます。彼の問いは、「世界の本質は何か」ではなく、「私たちはいかなる条件のもとで世界を経験しているのか」という方向へと転換しました。
知識がすべて経験に由来すると考えるだけでは、必然性や普遍性を説明できない。しかし、理性が独立に真理を生み出すと考える合理論にも戻れない。そこでカントは、経験を可能にする人間の認識能力そのものを分析対象としたのです。この態度を「超越論的」と呼びます。
このとき、イギリス経験論の成果は重要な役割を果たしました。ロックが示した生得観念批判、バークリーの認識と存在の結びつき、ヒュームの徹底した懐疑は、いずれも「人間の認識の側」に目を向ける視点を哲学にもたらしていました。
カントはこの視点を継承しつつ、感性や悟性といった認識の形式が、経験を構成する条件として働いていると考えます。
こうして哲学の関心は、世界そのものの本性を直接語る形而上学から、認識の条件を問う批判哲学(超越論的哲学)へと移行します。この転換は、経験論と合理論の単なる折衷ではありません。経験を出発点としながらも、その経験がどのような枠組みのもとで成立しているのかを問うという、新しい哲学の地平が開かれたのです。
もっとも、カントによってイギリス経験論が過去のものになったと考えるのは正しくありません。
バークリーやヒュームはカントを先取りして批判しているような面があり、カントがそれらを完全に乗り越えたと考える哲学者のほうが稀です。
現代的意義の観点から見ても、バークリーやヒュームの哲学は、現代科学の最先端とも呼応するポテンシャルを秘めています。