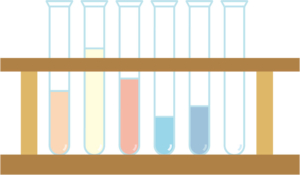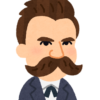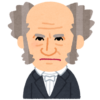科学哲学に楽しく入門できる名著『科学哲学の冒険』
「科学とは何か?」
この問いに明確な答えを出せる人は少ないでしょう。僕たちは日々、科学の恩恵を受けていますが、その理論や方法論の背後にある哲学について考えることはあまりありません。
しかし、科学の本質を理解することは、単なる知識の蓄積以上に価値があります。
・科学は本当に世界の真実を明らかにできるのか?
・科学的な知識はどこまで信頼できるのか?
こうした問いに答えるのが「科学哲学」という学問です。
本記事では、科学哲学の入門書として名高い 『科学哲学の冒険』(戸田山和久著) を紹介。その内容をわかりやすく解説します。
教授と生徒のあいだのフランクな会話で進行する構成。非常に読みやすいです。
科学哲学に入門するなら、これを最初の一冊にするとよいでしょう。
ただし注意点もあって、本書は中立の立場では書かれていません。科学的実在論と呼ばれる、科学哲学のなかではマイナーな立場から書かれています。
科学実在論とは何か?
科学的実在論とはなんでしょうか?
それは以下の2点を同時に認める立場です。
・世界には人間や科学から独立した存在と秩序がある(独立性テーゼ)
・科学はその秩序を知ることができる(知識テーゼ)
要するに、世界は人間とは独立した存在をもっていて、その世界の構造を科学は捉えることができると考えるのが科学実在論です。
こうやってみるとごくごく常識的な考え方ですよね。
しかし科学哲学の世界においては、このような考え方は少数派です。
反実在論と社会構成主義とは何か?
じゃあ他にどんな立場があるのかというと、代表的なのは反実在論と社会構成主義です。
上記の独立性テーゼと知識テーゼのうち、独立性テーゼを否定するのが社会構成主義です。
科学が対象としている世界は、科学者から独立した世界ではなく、科学者共同体という社会によって構成されたものであると考えるんですね。
一方、独立性テーゼを認めるものの、知識テーゼを否定するのが反実在論(名前がその中身を表していなくてややこしい)です。
科学者とは独立した世界はたしかに存在する、しかし科学はその構造を完全には知りえないと考えるのです。
そしてこの反実在論が科学哲学的にはスタンダードな模様。
科学者にもこのような考え方をする人は少なくないですよね。たとえば中谷宇吉郎の名著『科学の方法』(岩波新書)は、反実在論的なトーンが強いと思われます。
本書においては、戸田山和久は社会構成主義と反実在論を批判して、どうにか科学的実在論を擁護しようとするわけです。
とはいえその過程で科学的実在論以外の考え方もわかりやすく解説されていますから、科学哲学の入門書として読んでも問題はないと思います。
『科学哲学の冒険』の次に読むべき本はこれ
本書の巻末には読書案内もついていますが、そこで紹介されている内井惣七の『科学哲学入門 科学の方法・科学の目的』(世界思想社)がよりスタンダードなテキストとのこと。
本書とは逆に、反実在論のほうが科学をうまく説明できると考えている模様。内井のほうが、科学哲学においては王道なんですね。
本書の次の2冊目に読むべき本といえそうです。
カントの科学哲学
本書を読んで思ったのは、やっぱりカントの考え方ってユニークだなということ。
物自体としての世界がある。しかし人間はそれを認識できず、感性の形式(空間と時間)と悟性のカテゴリーによって加工された現象世界しか到達できない。しかしだからこそ科学法則は客観的かつ普遍的に妥当する、というもの。
物自体を認めるところは普通の実在論ぽいですが、それを認識できないとする点で違う。
しかし科学の対象は現象世界なのであり、現象世界については科学は認識できるとする点では反実在論ともだいぶ違う。
どちらかというと社会構成主義に近い面があるかもしれないですね。ただしカントの場合、科学の対象となる世界を構成するのは社会ではなく人間の感性・想像力・悟性なのですが。
あと本書ではポパーの反証主義がヒュームの懐疑論に沿ったものだという指摘も面白かったです。
科学哲学を含めた理数系の名著は、この記事でまとめて紹介しています↓