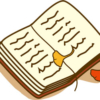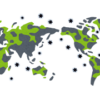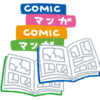コールリッジの詩人論『シェイクスピア論』
岩波文庫から出ている、コールリッジの『シェイクスピア論』。
英国ロマン派を代表する詩人コールリッジが、シェイクスピアについて語った講演録です。
かなりレアな本ですが、昨年中古屋でたまたま見つけました。
ずっと積ん読状態でしたが、グリーンブラットの『暴君』(岩波新書)でシェイクスピア熱が再燃した今こそチャンスと思い、なんとか読破。
この岩波文庫版は文字遣いが古めかしいので読むのが非常に大変。
また単なるシェイクスピア批評というよりコールリッジ自身の哲学や詩人論が随所に飛び出すため、内容的にもかなりヘヴィなものになっています。やや哲学書寄りな本ですね。
シェイクスピアに興味がある人なら楽しめるでしょう。
イギリスロマン派を代表する詩人コールリッジ
サミュエル・テイラー・コールリッジは18世紀から19世紀初頭にかけて活躍したイギリスの詩人。批評家、哲学者でもありました。
彼は、友人であるウィリアム・ワーズワースとともに「イギリスロマン主義」を代表する存在として知られています。
コールリッジは1772年にイングランド南西部のデヴォン州オッタリー・セント・メアリーで生まれました。父は牧師であり、学問好きの少年だったコールリッジは早くから読書に没頭します。ケンブリッジ大学に進学するも、経済的な困難や精神的な不安定さから中退。その後は詩作や思想活動に身を投じていきます。
彼の代表作の一つである『老水夫行』は、超自然的なモチーフと神秘的な雰囲気をたたえた長編詩で、ロマン主義の特質をよく表しています。
また『クリスタベル』『クブラ・カーン』といった作品も、幻想的な想像力と豊かな音楽性によって高く評価されています。
これらの詩はしばしば夢や幻覚といった主題を扱っていて、コールリッジが現実から逃避する傾向を持っていたこととも関係しているようです。
詩人としてだけでなく、批評家としての彼の業績も見逃せません。彼は『文学伝習』において、シェイクスピアの再評価や詩の本質に関する深い考察を展開し、後世の批評理論に大きな影響を与えました。
特に「想像力」と「空想」の区別や、ドイツ観念論の思想を英文学に応用した点が注目されます。
一方で、彼の人生は苦悩と矛盾に満ちていました。若いころから薬物に頼るようになり、特にアヘンの依存症が彼の心身を蝕んでいきました。家庭生活も不和に満ち、経済的にも苦労が絶えなかったようです。
彼の詩的才能は同時代から高く認められていましたが、その不安定な生活や未完成の作品群ゆえに、完全には理解されていなかった部分もありました。
しかし20世紀以降、批評家たちは彼の思想や詩の革新性に注目するようになり、現在ではワーズワースと並ぶロマン主義の巨匠として広く認められています。
コールリッジのシェイクスピア論
コールリッジは批評家としても有名でした。
ブラッドレーの『シェイクスピアの悲劇』(これも岩波文庫で読める)にも影響を与えたらしく、ブラッドレーの同書とコールリッジの本書が、英国におけるシャイクスピア論の双璧と言われていたそうです。
本書の特徴は第一に、シェイクスピアの人物造形を「一貫した性格を持つ人間として」捉えた点にあります。
たとえば当時の批評では、『ハムレット』の主人公が優柔不断で矛盾していると否定的にとらえる傾向がありましたが、コールリッジはその複雑さをこそリアリズムと心理的深さの証とみなし、ハムレットの内面を哲学的かつ詩的に解釈します。
彼はハムレットを「思索することで行動から遠ざかるタイプの人間」として読み解き、人間の精神の弱さや分裂を文学的に表現したものとして高く評価したのです。
第二に、想像力の哲学に基づいた文学観を用いた点が重要です。
コールリッジは「想像力(Imagination)」と「空想(Fancy)」を区別します。そして、シェイクスピアは単なる空想家ではなく、深い「統合的な想像力」をもって人物や世界を創造していると論じました。
彼にとって想像力とは、異質な要素を統一し、調和させる精神的な働きであり、シェイクスピアの戯曲はこの想像力によって秩序をもった芸術となっているというのです。
第三の特徴は、ドイツ観念論の影響を受けた哲学的アプローチです。
コールリッジはカントやシェリングなどのドイツ哲学をイギリスに紹介した人物でもあり、それらの思想を批評に取り込みました。
彼は芸術作品を単なる娯楽や道徳的教訓ではなく、精神的体験とみなし、シェイクスピアの作品にもそのような深い精神的探究があるとしました。
また、当時の一般的な見方では、シェイクスピアは天才ではあるが無意識に作品を書いたという見解が主流でした。
これに対しコールリッジは、シェイクスピアは意識的に構成し、哲学的・心理学的洞察に満ちた計算された芸術家であるという見方を打ち出し、シェイクスピアを「意図をもった詩的創造者」として位置づけ直しました。
コールリッジのシェイクスピア論は、詩的直感と哲学的思索を融合させた独自の批評であり、後のイギリス文学批評に大きな影響を与えることになります。
とくに、人物造形の精緻な解釈や、芸術と想像力についての理論的な洞察は、後代の批評家たちの出発点となったといえるでしょう。
現在でもコールリッジのシェイクスピア論は、近代批評の原点の一つとして高く評価されています。
本書で扱われるシェイクスピア作品は多岐にわたります。
前編と後編にわかれているのですが、前編では一般的な批評が、後半では個別の作品論が展開されます。
後半の作品論では以下の6つの作品が論じられていきます。
・ロミオとジュリエット
・ジュリアス・シーザー
・ハムレット
・オセロ
・リア王
・マクベス
シェイクスピアについての批評部分では、キャラクターについて永遠性を指摘するところがもっとも印象的でした。「何人といえども、シェイクスピアの作品中に、見るとはなしに自分の姿を見せつけられる」(コールリッジ『シェイクスピア論』)
詩人は過去のことを記録していながら、そこに不思議なほどまでに未来の影をも投じ、そして、過去でもなければ未来でもなくして、人間性そのもののなかに存する永久不変なものの状態をどんなにかすかにでも必ず感じさせ、またどんなに朧げにでも必ず見せるのである。
(同書)
これはシェイクスピアの読者であれば納得すると思う。そういえばドストエフスキーにも同じような能力がありますよね。
また本書は、シェイクスピア作品の批評部分だけでなく、詩人論について語られた箇所も面白いです。
コールリッジは「敬虔の念なき詩人はありえない」とし、詩歌と宗教の根源に同一のエネルギーを見定めます。
そして詩人については次のようにいいます(文字遣いは現代文にアレンジしてあります)
詩人とは成人してなお童子のような純情と素朴さとを失わない人、習慣に屈服し、あるいは俗習に拘束されることのない魂を有し、童子のような新鮮な気持ちと、驚異の念とを持って事象を観照する人、さらにこれとともに、成人した時の聡明な研究能力をも併せ持ち、知識の発見につれてますます驚嘆の念を加え、知識がもはや驚嘆を許さなくなる時は、再び嬉々として童子のような畏敬の念に満ちた驚異の感情に帰る人である。
(コールリッジ『シェイクスピア論』)
詩人とは、宇宙の謎を解くための人であるとともに、彼はまたその謎が解かれていない所をも感ずる人でなければならない。物それ自身においてではなくして、世俗的な熱情や業務による知性の眼の曇りゆえに、陳腐になったものを斬新にする者は詩人である。
(同書)
ブラッドレーの『シェイクスピアの悲劇』もそうですが、できれば現代の文字遣いに直した新しいバージョンで出てほしいですね。関心さえあれば読めますが、かなりの忍耐力を要するので。
ついでに言っておくとコールリッジの詩が読みたいならこれまた岩波文庫から出ている対訳詩集シリーズが圧倒的におすすめです。
左ページに英語、右ページに日本語訳という構成。日本語訳で意味を汲み取りながら、原文にふれることができます。
詩は翻訳で読んでもほとんど意味がないですからね。原文で味わえる対訳シリーズこそが至高。
このシリーズは他にもワーズワースとかポーの対訳詩集も出ています。海外の詩を読みたいなら活用を強く推奨します。
シェイクスピアのおすすめ作品は、以下の記事でまとめて紹介しています↓