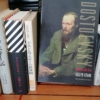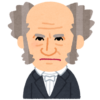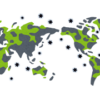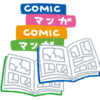ドストエフスキーの伝記ならグロスマンの『ドストエフスキイ』
加賀乙彦の『小説家が読むドストエフスキー』(集英社新書)を読んでいたら、ドストエフスキーの伝記ならこれがいちばん良いといってグロスマンの『ドストエフスキイ』(筑摩書房)が紹介されていました。
絶版で手に入りにくいのですが、後にたまたま中古で発見。速攻で買いましたよ。
出版されたのは1963年。
著者のグロスマンはソ連の人で、当時世界的にもよく知られたドストエフスキー研究者でした。
ボリュームは430ページ。二段組の構成ですので、ふつうの430ページより分量があります。
アンリ・トロワイヤによる文学的なドストエフスキー伝なんかと比べると、だいぶ落ち着いた文章です。
といってもドストエフスキーの生涯自体が異様なほど波乱万丈ですので、本作も自然と読み物としての面白さを持つにいたっています。読んでいて飽きるということはまったくありませんでした。
レオニード・グロスマンという人物
本書の著者レオニード・グロスマンは、20世紀前半のロシアおよびソビエト連邦における代表的な文学研究者・批評家であり、とくにドストエフスキー研究で知られる人物です。
グロスマンは1888年にロシア帝国時代のヴィリナ(現在のリトアニアのヴィリニュス)に生まれました。
彼はモスクワ大学で学び、文学と美学を中心に研究を進めました。若いころから文学評論家として活動を始め、革命前のロシアでは象徴主義やリアリズム文学に関心を寄せていたといいます。
十月革命以後もソビエト体制下で活動を続け、さまざまな文学者の研究を発表しますが、なかでももっとも有名なのがドストエフスキーに関する研究と伝記執筆です。
彼の代表作の一つが、1920年代から30年代にかけて執筆された『ドストエフスキー伝』です。
彼の伝記作品は、ソ連時代のイデオロギー的制約のなかでは比較的自由です(それでも偏りはありますが)。また、彼の文体は学術的でありながらも読みやすく、多くの読者にとってドストエフスキー理解の導入として価値あるものとなりました。
グロスマンのもう一つの特徴は、ドストエフスキーとフランス文学との関係にも注目していた点です。
とくにバルザックとの比較研究など、国際的な文学的視野を持ってドストエフスキーをとらえていて、その先駆的な姿勢は今日のドストエフスキー研究にも通じるところがあります。
晩年のグロスマンは、モスクワで教鞭を執りながら後進の指導にもあたりました。1965年にモスクワで亡くなっています。ソ連体制下で長く生きた知識人として、時代の制約のなかで文学的誠実さを守り続けた人物でした。
現在においても、レオニード・グロスマンのドストエフスキー研究は、ロシア語圏だけでなく、翻訳を通じて世界の研究者にも評価されています。
以下、グロスマンの『ドストエフスキイ』を、3つのポイントに注目してざっくり紹介します。
①ドストエフスキー伝の種本のひとつ
②作中の人物や出来事の成立過程がわかる
③社会主義的イデオロギーのバイアスには要注意
①ドストエフスキー伝の種本のひとつがこれ
ドストエフスキーには無数の伝記があります。
日本でも色々な本が出版されていますよね。日本でいちばん有名なのは小林秀雄の『ドストエフスキーの生活』ですかね。
しかし実は、種本と呼ばれる数冊の伝記があり、他の伝記はそれらの種本を参照しながら書いているというのが実情なのです。
ドストエフスキー本人の手紙といった一次資料、さらにドストエフスキーの家族や知人へのインタビュー、こういった情報源に直接あたった種本は多くないのです。
そしてその種本のなかの一つが本書、グロスマンの『ドストエフスキイ』(筑摩書房)です。
グロスマンは一次資料を駆使しまくってこの本を書いていますから、他の伝記とはその点で別格の地位にあるわけです。
②ドストエフスキーのインスピレーションの源がわかる
ドストエフスキーにはきわめて独特の作風がありますよね。哲学的な深みが非現実的なレベルにまで達するのですが、同時に登場人物には異様なリアリティがある。
ドストエフスキー本人はこれを「真のリアリズム」と呼んでいます。
だれにも真似できないこの作風を、彼はどうやって実現していたのか?本書を読むと、その秘密の一部が解明されます。
ドストエフスキーは、実は現実世界からネタをもってくるんですね。人物にせよ出来事にせよ、現実の日常にモデルがある。
親族とか友人とか文学仲間とか革命サークルの知人とか、そういう人をモデルにしてキャラクターを創り上げる。革命とか殺人とか家庭のいざこざとかにも、現実に起こったできごとを転用する。新聞を読み、ロンドンのスラム街を観察し、材料をかき集める。
そしてそれをアレンジし、哲学的な深みを与える。この順序が重要なのだと思います。
ドストエフスキーといえば思想的な天才性が注目されがちですよね。しかし本書を読むと、外部世界に向ける観察眼という点でも彼が尋常の作家ではないのだとわかります。
彼がどのような事件や人物に着目し、それを作品に活かしたのか。グロスマンはそれを教えてくれます。
スタヴローギンのモデルはスペシネフ
一例としてスペシネフに触れておきましょう。ペトラシェフスキーの会合でドストエフスキーが親しくなった人物です。
ペトラシェフスキーの会合というのは、ロシアに革命を起こそうとする一味の集まり。ドストエフスキーがこれに関与したために、当局から逮捕されてしまったことは有名です。
このスペシネフが強烈なカリスマだったらしい。ペトラシェフスキーなど相手にならないと言われています。
あのバクーニンがスペシネフについて語っていますので、少し引用してみましょう。
彼はいろんな点で注目すべき人物です。聡明で、金持ちで、教養がある上に美男子で、顔立ちはまことに気品があるし、落ち着き払って冷たい感じではあるけれども、落ち着いた力というものはみなそうですが、信頼感を植え付けるような、そういう容貌です。要するに、足の先から頭のてっぺんまでジェントルマンなのです。
(グロスマン『ドストエフスキイ』北垣信行訳)
バクーニンのスペシネフ評はこの後も続くのですが、ドストエフスキーの読者なら、あるキャラクターが想起されたかと思います。そう、いかにもスタヴローギンなんですよね。
実際、著者のグロスマンも、ドストエフスキーはスペシネフをモデルにしてスタヴローギンを創造したと言い切っています。
ドストエフスキーはこのスペシネフに精神的に支配されてしまったらしい。この人物から離れたい、しかし離れることができない、という精神状況。後年になってもこのことがトラウマとして記憶に刻まれていたそうです。
『悪霊』においてピョートルやシャートフやキリーロフは、謎の精神的支配力をスタヴローギンから受け続けますよね。おそらくあれはドストエフスキーの実体験に基づいた描写なんですね。だから迫力があるのかもしれません。
本書にはスペシネフの思想内容についても興味深い記述が見られます。
スペシネフはキリスト教の歴史を研究し、古代のキリスト教団の活動および影響力に驚嘆したらしい。
そして、自らの社会的野望(ロシアに革命を起こすこと)を実現するためには、このキリスト教団に類する組織を作り上げる必要がある、と考えていたというのです。
このスペシネフの考えを辿っていくと、『悪霊』の登場人物たちが企てようとしている陰謀が見えてきますね。さらに、『カラマーゾフの兄弟』のイワンの将来をも暗示しているかもしれません。
③社会主義イデオロギーのバイアスには要注意
本書を読んでいくと気づくのですが、グロスマンの記述にはソ連のイデオロギーが反映していると思われます。社会主義思想のバイアスが強いのです。
社会主義は人間の理性と進歩を信奉するシステムです。その立場からすると、キリスト教や無知無学の民衆を信じるドストエフスキーの思想は、反動的で時代遅れなものと映るのですね。
本書にはそうしたイデオロギーの影響が色濃いです。
したがってドストエフスキーのある面に関しては、グロスマンは不当な過小評価をしていると思っておいたほうがいいでしょう。ここは注意すべきですね。
ただ、日本の場合はドストエフスキーを実存主義的な観点から読み込んでいくバイアスが強すぎるので、ドストエフスキー作品に社会小説の次元を見出す本書の読みによって、ちょうどいいバランスがもたらされる可能性もあります。
以上、グロスマンの『ドストエフスキイ』を紹介しました。
絶版で手に入りにくくなっている本ですが、まぎれもない良書。中古で見かけたら、ドストエフスキーファンの方は購入したほうがよいかと思います。
その他、ドストエフスキー研究のおすすめ本は以下の記事で紹介しています↓
ドストエフスキー本人のおすすめ著作は以下の記事で解説↓