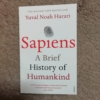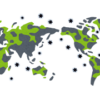マクニールを読むなら『疫病と世界史』がおすすめ
ウィリアム・マクニールは、20世紀を代表する歴史家のひとり。
日本でも彼の著作は多数文庫化されています。とくに有名なのは『世界史』ですが、実はあれは難しくて読みにくいです。
むしろ最初におすすめなのは、同じく中公文庫から出ている『疫病と世界史』のほう。
こっちのほうがテーマ性が見えやすいぶん話を理解しやすく、通読も容易です。
- 1. 『疫病と世界史』から読むのがおすすめな理由
- 2. マクニールの『疫病と世界史』はどんな本か?
- 3. 『疫病と世界史』への評価
- 4. 『疫病と世界史』と合わせて読みたい本
- 4.1. 感染症の世界史(石弘之)
- 4.2. 世界と日本がつながる感染症の文明史(茂木誠)
- 4.3. The Great Influenza(ジョン・M・バリー)
- 4.4. Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond(ソニア・シャー)
- 4.5. Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic(デイヴィッド・クォメン)
- 4.6. Phantom Plague: How Tuberculosis Shaped Our History(ヴィディヤ・クリシュナン)
- 4.7. The Ghost Map(スティーブン・ジョンソン)
『疫病と世界史』から読むのがおすすめな理由
マクニールを初めて読むなら『疫病と世界史』から入るのが良い選択になります。
多くの人にとって『世界史(The Rise of the West)』より読みやすいでしょう。
理由はいくつかあります。
まず、『疫病と世界史』はテーマが一貫しています。全編を通して「疫病」という明確な軸があり、どの章もその軸に沿って展開されます。そのため、多少細部が難しくても、読者は「今、何について読んでいるのか」を見失いにくい構造になっています。
一方で『世界史』は、文明間の相互作用という巨大なテーマを扱うため、政治、経済、軍事、宗教、文化が同時並行で語られ、読者に相当な集中力を要求します。
次に、『疫病と世界史』は叙述のスケールが適度です。世界全体を扱ってはいますが、扱う要因を意図的に絞っているため、議論が比較的コンパクトにまとまっています。具体的な疫病の流行や人口変動といった話題が多く、抽象度が高くなりすぎません。
これに対して『世界史』は、文明史全体を説明するために抽象的な概念や長期的構造の話が頻出し、文庫版であっても読書体験としてはかなり重いものになります。
さらに、『疫病と世界史』は問題提起型の本である点も読みやすさにつながっています。この本は「疫病を歴史の中心に置くと、世界史はどう見えるか」という問いを提示し、その答えを事例を通して示していきます。読者は常に仮説と検証の流れを追うことになり、学術書でありながら思考実験をしている感覚で読み進めることができます。
『世界史』のように、最初から最後まで巨大な総合史を構築する本とは、読書の質がかなり異なります。
マクニールの『疫病と世界史』はどんな本か?
マクニールの『疫病と世界史』は、人類史を「人間だけの営み」としてではなく、人間と病原体が長期にわたって相互作用してきた歴史として描き直すことにあります。
本書全体を貫く視点は、疫病が単なる付随的な出来事ではなく、文明の興亡や社会構造の変化を左右してきた根本的な要因であるという考え方です。
マクニールはまず、人類が狩猟採集生活から農耕生活へと移行したことが、疫病史の出発点であったと論じます。
定住と人口集中、家畜の飼育は、人と動物のあいだで病原体が行き来する環境を生み出しました。これによって、麻疹や天然痘のような集団感染型の病気が成立し、社会全体を周期的に襲うようになります。
疫病はここで初めて、個人の問題ではなく、集団と文明の問題となりました。
次にマクニールは、古代文明から中世にかけての世界を、疫病の分布と交通網の広がりという観点から描きます。
ユーラシア大陸では、交易路や戦争を通じて病原体が広範囲に移動し、地域ごとにある程度の免疫が形成されていきました。
一方、その均衡が崩れたとき、大規模な人口減少が起こります。ローマ帝国末期の疫病流行や、中世ヨーロッパを襲った黒死病はその典型であり、これらは単に人を殺しただけでなく、労働力不足、社会秩序の動揺、宗教意識の変化を引き起こしました。
特に黒死病について、マクニールはそれがヨーロッパ社会を内側から変質させた点を強調します。人口の激減によって農奴制が揺らぎ、労働者の地位が相対的に向上し、結果として近代的な社会への転換が促されたと考えます。
疫病は破壊的であると同時に、既存の社会構造を解体し、新しい秩序を準備する力を持っていたというわけです。
大航海時代以降の章では、疫病が世界規模で作用する様子が描かれます。
ヨーロッパ人が新大陸に持ち込んだ天然痘や麻疹は、アメリカ先住民社会を壊滅させました。これは軍事力や技術以上に決定的な要因であり、ヨーロッパによる征服と支配を可能にした背景には、生物学的な非対称性があったとマクニールは論じます。
ここでは、疫病が歴史の勝者と敗者を分けたという冷徹な視点が示されます。
近代に入ると、都市化と交通の高速化によって感染症はさらに広がりやすくなりますが、同時に医学と公衆衛生の発展によって、人類は一定の制御力を獲得していきます。
しかしマクニールは、ここで楽観論に与することはありません。疫病と人類の関係は終わったのではなく、形を変えて続いているにすぎないと述べます。
人類が病原体を制圧したかのように見える時代こそ、新たな感染症が現れる条件が整っていると警告します。
本書の終盤では、疫病を単なる医学の問題ではなく、生態系全体の中で捉える必要性が示されます。
人間社会は、政治的支配や経済構造という意味での「マクロな寄生関係」を持つ一方、病原体という「ミクロな寄生者」とも共存してきました。
この二重の寄生関係のバランスが崩れるとき、歴史は大きく動くというのが、マクニールの最終的な見取り図です。
『疫病と世界史』への評価
マクニールの『疫病と世界史』は発表以来、歴史学と疫学の両方の分野で強い反響を呼んだ重要な著作として受け止められています。
本書が刊行された当時は、感染症が世界史に与えた影響を大きく扱った書物はほとんどなく、疫病を単なる「出来事」ではなく歴史的な因果関係の一部として体系的に描いた点が評価されました。
疫病が人口や社会構造、帝国の興亡などにどのように作用したかを全地球的な視点で論じたことで、本書は従来の政治史や戦争史中心の歴史像に新たな視座をもたらしました。
一方で、評価が一様というわけではありません。
本書は1970年代に書かれたため、現在の疫学研究で用いられる分子生物学的なデータやゲノム解析の知見が反映されていない部分があり、現代の視点から見ると古典的な印象を持つ読者や研究者もいます。
また、疫病の影響を説明するための証拠が十分ではないとする指摘や、取り上げられる歴史事例がややヨーロッパ中心になっているとの批判もあります。
こうした批判は、歴史的な議論や疫学的解釈をさらに精緻にするために提示されてきたものであり、本書がその後の研究の出発点となっていることを示しています。
『疫病と世界史』と合わせて読みたい本
『疫病と世界史』の視点を最新の実証データ・現代疫学・近現代パンデミックの観点から補強したいとき、役立つ本はいくつもあります。
マクニールの本が世界史のマクロな構図を描いたのに対して、以下の本は個々の疫病の詳細、現代の疫学理論、パンデミックの実際の流行と対応、病原体の生態と人間社会との関係を深く理解する助けになるでしょう。
感染症の世界史(石弘之)
日本語で読みやすい形の世界史として、微生物と人類の関係を地球規模でたどっている本。
細菌やウイルスの進化や生態と、人間社会の歴史との相互作用を描くことで、マクニールの視点を現代的な感染症事情と結びつける助けになります。
世界と日本がつながる感染症の文明史(茂木誠)
日本語で書かれた世界史と日本史をつなげた感染症史で、古代から新型コロナウイルスまで広い時代を扱っています。
歴史と疫病との関係に最新の事例を加えたい読者に向いています。
The Great Influenza(ジョン・M・バリー)
1918~1920年のスペイン風邪(インフルエンザ)パンデミックを克明に描いた名著です。
感染症がどのように広まり、死者を出し、社会の機能を混乱させたかを具体的な事例と豊富な資料で説明しており、一次史料や当時の医療・軍事との関係も詳細に描かれています。
このパンデミックは世界史の転換点にもなった出来事で、マクニールの全体像を補うのに最適です。
Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond(ソニア・シャー)
コレラやエボラを含む複数の感染症を取り上げながら、病原体の発生源、伝播の仕方、社会・環境条件との関係を歴史的な視点と現代の疫学データで解きほぐす本。
歴史と科学を結びつける語りであり、感染症が世界各地でどのように作用してきたかを理解できます。
Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic(デイヴィッド・クォメン)
病気の起源を自然界の動物からの「スピルオーバー」として考える観点から、近年の新興感染症がどのように出現し、人間社会に広がるかを分析しています。
エボラ、SARS、HIV、そして将来のパンデミックの可能性についての科学的洞察があり、生態学的な視点を加えるときに有効です。
Phantom Plague: How Tuberculosis Shaped Our History(ヴィディヤ・クリシュナン)
結核という特定の病原体に焦点を当てた近年の歴史書で、19世紀から21世紀までの公衆衛生、政治、薬剤耐性、社会的不平等との関係を解説しています。
疫病が単なる医学的問題ではなく社会構造の問題でもあることを示す良い補完資料です。
The Ghost Map(スティーブン・ジョンソン)
19世紀ロンドンのコレラ流行を通じて、疫学の創始者ジョン・スノウの仕事や社会的反応を描いた作品。
当時の都市環境と感染症の関係、データと地図を使った科学的分析の萌芽を知るには最適で、歴史的ケーススタディとしても読み応えがあります。
これらの本は、それぞれ異なるアプローチで疫病がどのように人類社会に影響を及ぼしてきたのか、そして現在どのような仕組みやデータが理解につながるのかを補完してくれます。
マクニールの大局的な視点を出発点に、具体的な事例研究、近現代のパンデミック、疫学理論の発展を一緒に学ぶことで、より現代的でデータに裏打ちされた感染症史の理解が得られるでしょう。
世界史のおすすめ本まとめ記事はこちら↓