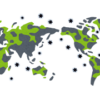シェイクスピアの『マクベス』はどう読まれてきたか【解釈の歴史】
シェイクスピア悲劇の最高傑作候補『マクベス』。
本作は、一見すると野心に駆られた男が破滅する単純な悲劇のようにも見えます。しかし、この作品は時代ごとにまったく異なる姿へと解釈されてきました。
道徳劇、政治劇、心理劇、言語の悲劇、そして虚無のドラマへと。
この記事では、代表的な解釈者の議論を手がかりに、『マクベス』がどのように読み替えられてきたのかを整理していきます。
マクベスはどんな作品か
まずは作品の全容を確認しておきましょう。
『マクベス』は、シェイクスピア四大悲劇の一つに数えられる作品。権力、暴力、そして人間の内面崩壊を描いた短く密度の高い悲劇であり、個人的には、これがシェイクスピアの最高傑作ではないかと思っています。
スコットランドを舞台に、勇敢な将軍マクベスが、魔女の予言をきっかけに王を殺し、王位を奪い、やがて破滅へと向かっていく過程が描かれます。
物語の筋自体は非常に単純です。しかし『マクベス』の特徴は、出来事の多さではなく、その一つ一つがもたらす心理的・象徴的な重さにあります。
王殺しという決定的な行為は物語の早い段階で起こり、その後は成功の物語ではなく、罪と恐怖がどのように人間を内側から崩していくかが集中的に描かれます。
『マクベス』は、道徳劇、政治劇、心理劇、言語の悲劇、さらには実存的な虚無の物語としてまで、時代ごとに異なる読みを許してきました。
以下、この作品がどのように読まれてきたのかを、代表的な解釈を通して見ていきます。
① 道徳劇的解釈(サミュエル・ジョンソン)
サミュエル・ジョンソンによる『マクベス』解釈は、18世紀を代表する道徳劇的な読みです。
ジョンソンはシェイクスピア全集の注釈者として決定的な役割を果たし、彼の評価は長らくシェイクスピア理解の基準となりました。
この立場では、マクベスは運命に翻弄された悲劇的人物ではなく、明確に「道徳的に誤った選択」を重ねた人物として描かれます。魔女の予言はあくまで誘惑のきっかけにすぎず、実際に王を殺すかどうかを決めたのはマクベス自身の意志です。したがって、悲劇の原因は超自然的な力ではなく、人間の内にある野心と道徳的弱さに求められます。
物語の展開も、この解釈では明快です。悪は一時的には成功するものの、その成功は決して持続せず、最終的には必ず罰を受けるという道徳的秩序が貫かれています。マクベスが王位を手に入れた直後から不安と恐怖に支配され、破滅へと向かっていく姿は、悪行がもたらす必然的な帰結として理解されます。
このような読み方によって、『マクベス』は単なる陰惨な悲劇ではなく、観客に道徳的教訓を与える作品として位置づけられました。そして同時に、シェイクスピアは人間の弱さを描きつつも、最終的には道徳秩序を肯定する「健全な道徳作家」であるという、18世紀的なシェイクスピア像が確立されたのです。
② 政治劇・王権論的解釈(ティリヤード)
E. M. W. ティリヤードによる『マクベス』解釈は、作品を個人の心理や性格の問題としてではなく、政治と宇宙秩序の観点から捉えるものです。
ティリヤードは『エリザベス朝の世界像』において、シェイクスピア作品の背後には当時共有されていた世界観、すなわち神・自然・国家が一体となった秩序観が存在すると論じました。
この立場では、王は単なる政治的指導者ではなく、神によって選ばれた存在であり、その統治は宇宙的秩序の一部を成しています。したがって王殺しは、個人的な犯罪にとどまらず、神意と自然法則に反する行為と見なされます。マクベスがダンカンを殺害した瞬間、政治的秩序だけでなく、宇宙全体の調和が破壊されたと理解されるのです。
作中で繰り返し描かれる自然の異変は、この解釈において重要な意味を持ちます。昼が夜のように暗くなることや、動物が異常な振る舞いを見せる描写は、単なる雰囲気づくりではありません。それらは、正統な王権が侵害されたことによって、自然界そのものが不安定化している徴候だとされます。自然の乱れは、すなわち政治秩序の乱れなのです。
このように読むと、マクベスはまず何よりも国家秩序を破壊した政治的存在となります。彼の悲劇性や内面的葛藤は副次的なものであり、中心にあるのは王権の正当性と秩序回復の問題です。
ただし、この解釈はシェイクスピアを秩序擁護の作家として強く位置づけるため、後の批評では「保守的すぎる」「作品の多義性を抑え込んでいる」といった批判も受けることになります。
③ 心理劇的解釈(ブラッドリー)
A. C. ブラッドリーによる心理劇的解釈は、『マクベス』理解において現在でも最も影響力の強い読みの一つです。
ブラッドリーは『シェイクスピアの悲劇』の中で、悲劇を外的事件の連鎖としてではなく、主人公の内面で進行する精神的プロセスとして捉えました。
この解釈において、魔女は悲劇の直接的な原因ではありません。予言はマクベスの中にすでに存在していた欲望を生み出すのではなく、それを表面化させる触媒にすぎないとされます。もし彼の内面に野心がなければ、魔女の言葉は何の力も持たなかったはずです。したがって悲劇の起点は超自然的存在ではなく、人間の心そのものに置かれます。
ブラッドリーがとくに重視したのは、マクベスの想像力です。彼は行為に先立って結果を鮮明に思い描いてしまうため、その想像が恐怖や罪悪感を増幅させます。空中に浮かぶ短剣やバンクォーの亡霊は、外界の怪異というよりも、良心と欲望の葛藤が生み出した内的幻影として理解されます。マクベスは冷酷な悪人というより、過剰な想像力ゆえに自らを追い詰めていく人物なのです。
このように、『マクベス』の悲劇性は、野心と良心、欲望と恐怖のあいだで引き裂かれる内面の崩壊にあります。ブラッドリーの読みは、マクベスを単純な悪役から解放し、弱さと葛藤を抱えた人間として描き出しました。
その結果、読者や観客が感情移入できる「共感可能なマクベス」という像が確立され、現代に至るまで『マクベス』解釈の中心的な枠組みとして受け継がれているのです。
④ レディ・マクベス再評価(ジェンダー論)
20世紀後半以降のフェミニズム批評やジェンダー論の文脈では、レディ・マクベスの評価は大きく変化しました。
キャロル・アスプやリンダ・ボーズといった研究者は、彼女を単なる冷酷な「悪女」として描く従来の読みを批判し、当時の性別役割や権力構造の中で行動せざるをえなかった人物として捉え直します。
この解釈では、レディ・マクベスの過激な言動は、生来の残酷さの表れではありません。彼女は男性中心の政治社会において、行為し、決断し、権力を握るためには「男性的」とされる強さや冷酷さを演じる必要があったとされます。彼女の有名な祈りに見られる自己否定は、自然な女性性を捨て去り、権力の言語に身を合わせようとする必死の試みとして読まれます。
しかし、その適応は深い代償を伴います。行為を主導していた前半とは対照的に、王殺しの後、彼女は次第に言葉を失い、行動からも排除されていきます。夢遊病の場面で噴き出す罪悪感や恐怖は、単なる天罰や道徳的報いではなく、長く抑圧されてきた感情が制御を失って表面化した結果だと理解されます。
このように、ジェンダー的再評価においてレディ・マクベスの狂気は「罰」ではなく、権力構造に適応しようとしたこと自体が生み出した悲劇的帰結として描かれます。この読みは、『マクベス』を夫婦の犯罪劇としてだけでなく、性別と権力の関係を鋭く問う作品として浮かび上がらせます。
⑤ 言語・超自然の解釈(エンプソン)
ウィリアム・エンプソンによる言語中心の解釈は、『マクベス』を超自然的な運命劇としてではなく、言葉そのものが悲劇を生み出す作品として読み直すものです。
エンプソンは『曖昧の七つの型』において、文学における意味の多義性がいかに読者や登場人物の理解を揺さぶるかを示しましたが、その視点は『マクベス』解釈にも強く影響を与えました。
この立場では、魔女の予言は未来を一義的に示す確定的な言明ではありません。それらの言葉は本質的に曖昧で、複数の意味や解釈の可能性を孕んでいます。問題は予言が真か偽かという点ではなく、その曖昧な言葉をマクベスがどのように理解し、信じ、行為へと結びつけたかにあります。
たとえば、予言は必ずしもマクベスに殺人を命じてはいません。しかし彼は、言葉の一部だけを都合よく読み取り、そこに自らの欲望を重ね合わせてしまいます。その結果、曖昧さを保持したままの言語が、確定した意味をもつかのように誤認され、取り返しのつかない行為へとつながっていきます。
このように見ると、マクベスは運命に敗れたのではなく、言語の曖昧さを読み違えた人物だと言えます。言葉は現実を反映するだけでなく、人間の行為を方向づけ、世界のあり方そのものを変えてしまうのです。
この言語重視の読みは、後にポスト構造主義へと発展し、意味の不安定さや解釈の暴力性を問う現代批評の重要な前提となりました。
⑥ 実存主義的・虚無的解釈(ヤン・コット)
ヤン・コットによる実存主義的・虚無的解釈は、『マクベス』を20世紀、特に戦後世界の感覚と深く結びつけて読み直す試みです。
コットは『シェイクスピアはわれわれの同時代人』の中で、シェイクスピア作品を歴史的遺物としてではなく、現代人の経験に直接訴えかける同時代的テクストとして捉えました。
この解釈において、『マクベス』の世界は最初から意味や救済を約束された場所ではありません。善と悪の対立や道徳的秩序はもはや決定的な力を持たず、歴史は進歩するのではなく、同じ暴力を繰り返しながら循環するだけのものとして描かれます。王が倒れれば別の王が現れ、権力は形を変えて移動するにすぎません。
コットが重視したのは、物語後半におけるマクベスの独白です。
あすが来、あすが去り、そしてまたあすが、こうして一日一日と小きざみに、時の階を滑り落ちて行く、この世の終わりに辿り着くまで。いつも、きのうという日が、愚か者の塵にまみれて死ぬ道筋を照らしてきたのだ。消えろ、消えろ、つかの間の燈し火!人の生涯は動き回る影にすぎぬ。あわれな役者だ、ほんの自分の出番のときだけ、舞台の上で、みえを切ったり、喚いたり、そしてとどのつまりは消えてなくなる。白痴のおしゃべり同然、がやがやわやわや、すさまじいばかり、何の取りとめもありもせぬ。
(シェイクスピア『マクベス』福田恆存訳)
人生を「歩く影」や「愚かな話」と語る言葉には、行為の意味が失われた世界に投げ出された人間の感覚が凝縮されています。そこにあるのは悔恨や教訓ではなく、徹底した虚無です。この感覚こそが、二度の世界大戦を経験した20世紀の人間にとって、切実な現実として響いたのです。
このように読むと、『マクベス』は野心や道徳をめぐる悲劇ではなく、終わりなき暴力と権力闘争が続く戦時世界の寓話となります。コットの解釈によって、マクベスはベケットやカフカの作品に登場する不条理な人物像と並べて読まれるようになり、『マクベス』は近代以降の実存的な不安を先取りした作品として、新たな位置づけを与えられたのです。
⑦ 柄谷行人のマクベス論
最後に、日本人の手による有名なマクベス論を紹介しておきます。
戦後日本を代表する文芸批評家・哲学者の柄谷行人によるマクベス論です。『意味という病』に収録。
普通、マクベスはリチャード三世のような人物と同じタイプとみなされます。彼は野心に満ちたマキャベリストである、と。
しかし柄谷はその見方を否定し、マクベスは近代的自我が行きつくところまで行き、ついには自らの根拠をも掘り崩した結果として現れた、空虚な主体であると見なします。マクベスにおいては、世界の「自然性」や「自明性」が失われています。
現実との接触を失った彼の観念は暴走し、マクベス夫人という他者の導きによってそれが現実化されます。それが現実となったことに、だれよりもマクベスが驚いているのです。
しかしマクベス夫人もまた、自然性とは無縁の存在でした。意味の仮構に疲れ果てたこの夫婦は、すべての意味が剝奪された虚無的な終わりへと猛進していきます。
シェイクスピアのおすすめ作品まとめはこちら↓